第83回 雨の気配:早苗 早苗取る 田植え
第83回【目次】
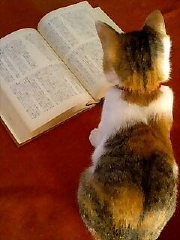
* 和歌
* 散文
* みやとひたち
 若楓 22.6.2 東京都清瀬市
若楓 22.6.2 東京都清瀬市
1 雨の気配
今年は6月7日が二十四節気でいう「芒種(ぼうしゅ)」、「芒(のぎ)ある穀類、稼種する時也」と、『暦便覧』(天明年間[天明7年(1787)]から長らく読まれてきている暦の解説書)にある節気です。芒(のぎ)というのは棘状の突起のことで、芒(のぎ)ある穀類と言えば、その代表は稲です。籾殻の付いたままの粒をご想像下さい。先の鋭く尖ったあの部分が「芒」です。「芒種」のこの頃は、昔はこうした穀物の種を播く時期で、その種は間もなく来る梅雨の雨に芽を出し、育つのです。「芒種」という言葉は、古代はこの時期が稲作の一年の始まり、農耕事始めの時期であったことを残す言葉です。
 22.6.2 東京都清瀬市
22.6.2 東京都清瀬市
日本の歌の伝統でも、この時期は季節の花や鳥を歌うほかに、珍しく労働を歌います。田植えです。
 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市
古くは『万葉集』に苗代水(なわしろみづ)という言葉が出てくるところから、そこに稲作の形跡を見ますが、『万葉集』では田植えそのものを詠むことはしていないようです。恋人同士の遣り取り(相聞歌)の中で、「くっきりと見通せない」ということを、田植えで濁る苗代水になぞらえて「(濁っていて)分からない」と表現するために、比喩的に用いているばかりです〈※1〉。
〈※1〉言出[ことで]しは誰[た]が言[こと]なるか小山田[をやまだ]の
苗代水[なはしろみづ]の中淀[なかよど]にして
(「紀女郎[きのいらつめ]、家持に報へ贈る歌一首」として)
 22.5.31 東京都清瀬市
22.5.31 東京都清瀬市
2 早苗取る
平安時代の作品になると、いろいろな作品に、この時期の田植えは目に付くようになります。
昨日こそ早苗取りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く
「古今和歌集」172
この歌は、御覧の通り秋の歌ですが、「古今和歌集」に採られ、その後の京都の貴族には周知の歌でした。詠み人知らずの歌でこれに採られると言うことは、「古今和歌集」を撰集していた九世紀末から十世紀始めにおいて、この歌の感興がすでに人々の共有するものであったことを意味しています。言うまでもない貴族社会、貴族が詠む歌ですが、平安貴族の眼にも稲田の様相が季節の移り変わりをしみじみ実感させる風景であったことがわかります。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市
この中で「早苗とり(早苗とる)」とあるのが、「田植え」を意味する言葉です。
素朴な稲作は、籾を直(じか)に農地に播いてそのまま生育を待つ、いわゆる直播きでしたが、やがて、苗床をつくり、若く育った苗、早苗を、水を引いた田に植え付ける農作に進化しました。「早苗取る」はその労働をそのまま表す言葉です。
 田植えを待つ早苗 22.6.5 埼玉県志木市
田植えを待つ早苗 22.6.5 埼玉県志木市
清少納言の「枕草子」に、田植えの記事が見えます。時は陰暦の五六月の頃、賀茂神社に参詣する途中のことです。
賀茂へまゐる道に、田植うとて、女の、あたらしき折敷[をしき]のやうなる
ものを笠に着て、いと多く立ちて、歌をうたふ、折れ伏すやうに、また、何ご
とするとも見えでうしろざまにゆく、いかなるにかあらむ、をかしと見ゆるほ
どに、郭公[ほととぎす]をいとなめう(無礼に、馬鹿にして)うたふ、聞く
にぞ心憂き。
「ほととぎす、おれ(おのれ、=お前)、かやつ(彼奴)よ、おれ鳴きてこそ、
われは田植うれ」
と歌ふを聞くも、いかなる人か、「いたくな鳴きそ」とはいひけん。仲忠が童
生ひ〈※2〉言ひ落とす人と、ほととぎす鶯におとるといふ人こそ、いとつら
うにくけれ。 「枕草子」226段
〈※2〉仲忠は「宇津保物語」の主要な登場人物の一人。遣唐使清原俊蔭の娘と
太政大臣の子息との間の子。「宇津保物語」は伝奇的な作品で、荒唐無
稽な浪漫的な内容を多く含む。俊蔭死後、拠り所のない娘は北山の奥の
大木の空洞を熊から譲り受け、住まいとして、北山の動物に混じって森
の中で暮らし、幼少の仲忠を育てた。その特殊な生い立ち(童生ひ)を、
都をちょっとでも離れて育った者を蔑視するのと同じ基準で、育ちが悪
いと見る評価があった。
「枕草子」の記述でも、一日仕事になるからでしょう、女性は菅笠を被って田に入っています。後ろ向きに移動しながら苗を田に植え付けて行くという動作は、機械化されるまでの田植えの作業として近年まで普通に見られた光景です。今日でも、極く小規模な農地の場合、また丁寧な農作の方法に、この手植えの仕方は続いています。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市
3 時鳥に命じられて
清少納言の記述は、その作業風景を貴族として珍しく見たこと(「いかなるにかあらむ、をかし」)から始まり、興味は田植え歌の歌詞に移ります。
大勢で労働をしながら歌うのは、「万葉集」の東歌などにも見え、古代からの自然の営みなのでしょう。田植えの折にもそれはあり、現在でも各地にそれぞれの田植え歌が残ります。「枕草子」に見えるのもその一つで、季節の鳥である時鳥(ほととぎす)が歌われています。
「ほととぎす、おれ(二人称のおのれ、=お前)、かやつ(彼奴)よ、
おれ鳴きてこそ、われは田植うれ」
「ほととぎすよ、お前が鳴くから、我らは田を植えるのだが...」と歌うもので、助詞「こそ」と已然形「植うれ」の古典語の係り結びの語法からすると、ここのニュアンスは「したくないのだが仕方なく」といった空気であると思われます。単に時鳥の鳴く季節が訪れたことだけを言う表現ではありません。
田植えは重い労働なのです。辛いけれども収穫のもと、生存がかかっていますから、これをしないことなどはもちろん想定にもないのですが、厳しい労働に際して、「時鳥のヤツが鳴くから」と、重い腰を上げる理由にしているのです。古い時代の庶民のユーモアというべきでしょう。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市
ユーモアのセンスでは余人にひけを取らない清少納言ですが、ここでは田植え歌の遊び心に付き合うことが出来なかったようです。「(時鳥を無礼に扱って歌うのが)聞くにぞ心憂き」と無粋に腹を立てています。というのも、時鳥は清少納言のお気に入りの鳥で、「枕草子」にその気に入り具合は随所に看て取れます。ここでも、「宇津保物語」の御贔屓の登場人物仲忠と並べて時鳥を挙げ、この鳥を嘗めてあしらう人はたいそう癪に障って腹立たしいと、真顔で述べています。
 マガモ 22.6.5 東京都清瀬市
マガモ 22.6.5 東京都清瀬市
「枕草子」では、こうしたいささか大人げなく見える率直な物言いに折々遇います。多分、良い意味で清少納言は大人げない人だったのだろうと想像しています。人が大人になるといつしか失われがちな種類の心、みずみずしい好奇心や計算の無い素直な心遣い、ある種清潔な感性を、その後もずっと持ち続けた人であるように、「枕草子」の記述に私は感じています。
 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市
こういう人は、言動が元気で闊達で何やら達者に見えても強(したた)かでなく、学があってその方面で賢くても恐らく損得勘定に関心が薄く、間違っても老後のために蓄財するような用心深さはなさそうです。鎌倉時代の文学評論「無名草子」などをはじめとして、清少納言が後に零落したという伝えが所々に見られるのは、後半生がはっきりしない著名人には珍しくない、根も葉もない伝説かもしれません。権力者藤原道長の側に付かなかった清少納言の末路は、「紫式部日記」が酷評しているように、意図的に悪く形造られる向きもあったかもしれません。しかし、本当に零落していたとしても不思議はない気もいたします。しかしそうだとして、子供のようにつよい清少納言はあまり苦にしなかったのではないかと思ったりします。
 猫デモ オモシロイ 「枕草子」
猫デモ オモシロイ 「枕草子」
時鳥は古代から多くの文献に登場し、さまざまな表記で表される鳥ですが、その中に「田鵑」などとあるのは、やはり稲作、この頃なら田植えと関係づけた表記のように思われます。伝承が多く、歌にもよく詠まれ、親しまれた鳥なのでしょう、呼び名にも、いもせ鳥、ときつ鳥、卯月鳥、たそがれ鳥、たまさか鳥、たまむかへ鳥、ぬばたま鳥、ももこゑ鳥、ゆふかげ鳥、しづこ鳥、しづ鳥、など、意味の良く分からないものまで含めると、果てしないまでたくさんの異名を持っています。清少納言は不服でしょうが、その数多い異名の中に、先の田植え歌の趣き通りの「しでの田長(たおさ)」、また「田長鳥」という呼び名も持っています。田長とは田植えにおいて、監督あるいは命令する役目でしょう。まさに時鳥が時期を告げ、命じて、人に田植えをさせる、という筋の命名です。
また、「ときつ鳥」と言う名は、そのまま時鳥の表記のもとになった呼称と思われますが、いったい何の「時」なのでしょう。
12世紀後半の歌学書「袖中抄」(顕昭著 文治年間〈1185-1190頃〉に成立)に、こんな記事があります。
「(ほととぎすの異名の一つ)しでのたおさ」とは「しづのたおさ」といふなり。ほととぎすは勧農の鳥とて、過時不熟と鳴といへり。
「しづ(賤)の田長」という解釈はいかにもありそうですが、それはともかく、時鳥は農業を勧める鳥であって、「過時不熟(時を過ぐさば熟せず=時期を逸せば実らない)」と鳴く、というのが眼を引きます。この鳥の名に冠する「時」とは農事の「時」、おそらく田植えのタイミングを指すのだろうと推察されるのです。初夏、しかるべき季節にこの鳥が鳴くのは、まさに「今が田植えの時期である、今を弛むな」という叱咤に仮想することができたのでしょう。ほととぎすは声が大きくくっきりしているのが、平安人の好みの別かれるところでした。
田植えが機械化され、集団で手植えするという形態がなくなるにつれて、田植え歌は歌われる機会もほとんどなくなりました。現在各地に残っている田植え歌に、植え手とは別に、田の脇や畦道で労働の伴奏のようにただ歌うという形態があるのは、かつては田植え歌そのものにも稲作を支える呪術的な働きが意識されていたのかも知れません。敷島の大和は瑞穂の国、稻は特別に大切な作物であったことは間違いありません。お米は本当に美味しいですしね。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市
このたびは、文例には田植え、早苗に関わるものを集めました。田植え歌を御紹介することも試みましたが、口承の歌であり、そもそも単語の意味の分からないところ、また擬音語、感嘆詞、合いの手、の混ざり合った歌詞は文字に起こすのも困難なものが多く、作品の文例には難しいと諦めました。しかし多くの中には、文字にして、かつその心を伝えられる田植え歌もあるかも知れず、今後の収拾の課題といたします。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市
 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市
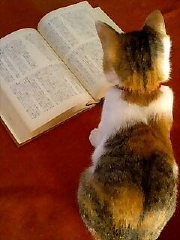
* 和歌
* 散文
* みやとひたち
 若楓 22.6.2 東京都清瀬市
若楓 22.6.2 東京都清瀬市1 雨の気配
今年は6月7日が二十四節気でいう「芒種(ぼうしゅ)」、「芒(のぎ)ある穀類、稼種する時也」と、『暦便覧』(天明年間[天明7年(1787)]から長らく読まれてきている暦の解説書)にある節気です。芒(のぎ)というのは棘状の突起のことで、芒(のぎ)ある穀類と言えば、その代表は稲です。籾殻の付いたままの粒をご想像下さい。先の鋭く尖ったあの部分が「芒」です。「芒種」のこの頃は、昔はこうした穀物の種を播く時期で、その種は間もなく来る梅雨の雨に芽を出し、育つのです。「芒種」という言葉は、古代はこの時期が稲作の一年の始まり、農耕事始めの時期であったことを残す言葉です。
 22.6.2 東京都清瀬市
22.6.2 東京都清瀬市日本の歌の伝統でも、この時期は季節の花や鳥を歌うほかに、珍しく労働を歌います。田植えです。
 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市古くは『万葉集』に苗代水(なわしろみづ)という言葉が出てくるところから、そこに稲作の形跡を見ますが、『万葉集』では田植えそのものを詠むことはしていないようです。恋人同士の遣り取り(相聞歌)の中で、「くっきりと見通せない」ということを、田植えで濁る苗代水になぞらえて「(濁っていて)分からない」と表現するために、比喩的に用いているばかりです〈※1〉。
〈※1〉言出[ことで]しは誰[た]が言[こと]なるか小山田[をやまだ]の
苗代水[なはしろみづ]の中淀[なかよど]にして
(「紀女郎[きのいらつめ]、家持に報へ贈る歌一首」として)
 22.5.31 東京都清瀬市
22.5.31 東京都清瀬市2 早苗取る
平安時代の作品になると、いろいろな作品に、この時期の田植えは目に付くようになります。
昨日こそ早苗取りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く
「古今和歌集」172
この歌は、御覧の通り秋の歌ですが、「古今和歌集」に採られ、その後の京都の貴族には周知の歌でした。詠み人知らずの歌でこれに採られると言うことは、「古今和歌集」を撰集していた九世紀末から十世紀始めにおいて、この歌の感興がすでに人々の共有するものであったことを意味しています。言うまでもない貴族社会、貴族が詠む歌ですが、平安貴族の眼にも稲田の様相が季節の移り変わりをしみじみ実感させる風景であったことがわかります。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市この中で「早苗とり(早苗とる)」とあるのが、「田植え」を意味する言葉です。
素朴な稲作は、籾を直(じか)に農地に播いてそのまま生育を待つ、いわゆる直播きでしたが、やがて、苗床をつくり、若く育った苗、早苗を、水を引いた田に植え付ける農作に進化しました。「早苗取る」はその労働をそのまま表す言葉です。
 田植えを待つ早苗 22.6.5 埼玉県志木市
田植えを待つ早苗 22.6.5 埼玉県志木市 清少納言の「枕草子」に、田植えの記事が見えます。時は陰暦の五六月の頃、賀茂神社に参詣する途中のことです。
賀茂へまゐる道に、田植うとて、女の、あたらしき折敷[をしき]のやうなる
ものを笠に着て、いと多く立ちて、歌をうたふ、折れ伏すやうに、また、何ご
とするとも見えでうしろざまにゆく、いかなるにかあらむ、をかしと見ゆるほ
どに、郭公[ほととぎす]をいとなめう(無礼に、馬鹿にして)うたふ、聞く
にぞ心憂き。
「ほととぎす、おれ(おのれ、=お前)、かやつ(彼奴)よ、おれ鳴きてこそ、
われは田植うれ」
と歌ふを聞くも、いかなる人か、「いたくな鳴きそ」とはいひけん。仲忠が童
生ひ〈※2〉言ひ落とす人と、ほととぎす鶯におとるといふ人こそ、いとつら
うにくけれ。 「枕草子」226段
〈※2〉仲忠は「宇津保物語」の主要な登場人物の一人。遣唐使清原俊蔭の娘と
太政大臣の子息との間の子。「宇津保物語」は伝奇的な作品で、荒唐無
稽な浪漫的な内容を多く含む。俊蔭死後、拠り所のない娘は北山の奥の
大木の空洞を熊から譲り受け、住まいとして、北山の動物に混じって森
の中で暮らし、幼少の仲忠を育てた。その特殊な生い立ち(童生ひ)を、
都をちょっとでも離れて育った者を蔑視するのと同じ基準で、育ちが悪
いと見る評価があった。
「枕草子」の記述でも、一日仕事になるからでしょう、女性は菅笠を被って田に入っています。後ろ向きに移動しながら苗を田に植え付けて行くという動作は、機械化されるまでの田植えの作業として近年まで普通に見られた光景です。今日でも、極く小規模な農地の場合、また丁寧な農作の方法に、この手植えの仕方は続いています。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市3 時鳥に命じられて
清少納言の記述は、その作業風景を貴族として珍しく見たこと(「いかなるにかあらむ、をかし」)から始まり、興味は田植え歌の歌詞に移ります。
大勢で労働をしながら歌うのは、「万葉集」の東歌などにも見え、古代からの自然の営みなのでしょう。田植えの折にもそれはあり、現在でも各地にそれぞれの田植え歌が残ります。「枕草子」に見えるのもその一つで、季節の鳥である時鳥(ほととぎす)が歌われています。
「ほととぎす、おれ(二人称のおのれ、=お前)、かやつ(彼奴)よ、
おれ鳴きてこそ、われは田植うれ」
「ほととぎすよ、お前が鳴くから、我らは田を植えるのだが...」と歌うもので、助詞「こそ」と已然形「植うれ」の古典語の係り結びの語法からすると、ここのニュアンスは「したくないのだが仕方なく」といった空気であると思われます。単に時鳥の鳴く季節が訪れたことだけを言う表現ではありません。
田植えは重い労働なのです。辛いけれども収穫のもと、生存がかかっていますから、これをしないことなどはもちろん想定にもないのですが、厳しい労働に際して、「時鳥のヤツが鳴くから」と、重い腰を上げる理由にしているのです。古い時代の庶民のユーモアというべきでしょう。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市ユーモアのセンスでは余人にひけを取らない清少納言ですが、ここでは田植え歌の遊び心に付き合うことが出来なかったようです。「(時鳥を無礼に扱って歌うのが)聞くにぞ心憂き」と無粋に腹を立てています。というのも、時鳥は清少納言のお気に入りの鳥で、「枕草子」にその気に入り具合は随所に看て取れます。ここでも、「宇津保物語」の御贔屓の登場人物仲忠と並べて時鳥を挙げ、この鳥を嘗めてあしらう人はたいそう癪に障って腹立たしいと、真顔で述べています。
 マガモ 22.6.5 東京都清瀬市
マガモ 22.6.5 東京都清瀬市「枕草子」では、こうしたいささか大人げなく見える率直な物言いに折々遇います。多分、良い意味で清少納言は大人げない人だったのだろうと想像しています。人が大人になるといつしか失われがちな種類の心、みずみずしい好奇心や計算の無い素直な心遣い、ある種清潔な感性を、その後もずっと持ち続けた人であるように、「枕草子」の記述に私は感じています。
 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市こういう人は、言動が元気で闊達で何やら達者に見えても強(したた)かでなく、学があってその方面で賢くても恐らく損得勘定に関心が薄く、間違っても老後のために蓄財するような用心深さはなさそうです。鎌倉時代の文学評論「無名草子」などをはじめとして、清少納言が後に零落したという伝えが所々に見られるのは、後半生がはっきりしない著名人には珍しくない、根も葉もない伝説かもしれません。権力者藤原道長の側に付かなかった清少納言の末路は、「紫式部日記」が酷評しているように、意図的に悪く形造られる向きもあったかもしれません。しかし、本当に零落していたとしても不思議はない気もいたします。しかしそうだとして、子供のようにつよい清少納言はあまり苦にしなかったのではないかと思ったりします。
 猫デモ オモシロイ 「枕草子」
猫デモ オモシロイ 「枕草子」時鳥は古代から多くの文献に登場し、さまざまな表記で表される鳥ですが、その中に「田鵑」などとあるのは、やはり稲作、この頃なら田植えと関係づけた表記のように思われます。伝承が多く、歌にもよく詠まれ、親しまれた鳥なのでしょう、呼び名にも、いもせ鳥、ときつ鳥、卯月鳥、たそがれ鳥、たまさか鳥、たまむかへ鳥、ぬばたま鳥、ももこゑ鳥、ゆふかげ鳥、しづこ鳥、しづ鳥、など、意味の良く分からないものまで含めると、果てしないまでたくさんの異名を持っています。清少納言は不服でしょうが、その数多い異名の中に、先の田植え歌の趣き通りの「しでの田長(たおさ)」、また「田長鳥」という呼び名も持っています。田長とは田植えにおいて、監督あるいは命令する役目でしょう。まさに時鳥が時期を告げ、命じて、人に田植えをさせる、という筋の命名です。
また、「ときつ鳥」と言う名は、そのまま時鳥の表記のもとになった呼称と思われますが、いったい何の「時」なのでしょう。
12世紀後半の歌学書「袖中抄」(顕昭著 文治年間〈1185-1190頃〉に成立)に、こんな記事があります。
「(ほととぎすの異名の一つ)しでのたおさ」とは「しづのたおさ」といふなり。ほととぎすは勧農の鳥とて、過時不熟と鳴といへり。
「しづ(賤)の田長」という解釈はいかにもありそうですが、それはともかく、時鳥は農業を勧める鳥であって、「過時不熟(時を過ぐさば熟せず=時期を逸せば実らない)」と鳴く、というのが眼を引きます。この鳥の名に冠する「時」とは農事の「時」、おそらく田植えのタイミングを指すのだろうと推察されるのです。初夏、しかるべき季節にこの鳥が鳴くのは、まさに「今が田植えの時期である、今を弛むな」という叱咤に仮想することができたのでしょう。ほととぎすは声が大きくくっきりしているのが、平安人の好みの別かれるところでした。
田植えが機械化され、集団で手植えするという形態がなくなるにつれて、田植え歌は歌われる機会もほとんどなくなりました。現在各地に残っている田植え歌に、植え手とは別に、田の脇や畦道で労働の伴奏のようにただ歌うという形態があるのは、かつては田植え歌そのものにも稲作を支える呪術的な働きが意識されていたのかも知れません。敷島の大和は瑞穂の国、稻は特別に大切な作物であったことは間違いありません。お米は本当に美味しいですしね。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市このたびは、文例には田植え、早苗に関わるものを集めました。田植え歌を御紹介することも試みましたが、口承の歌であり、そもそも単語の意味の分からないところ、また擬音語、感嘆詞、合いの手、の混ざり合った歌詞は文字に起こすのも困難なものが多く、作品の文例には難しいと諦めました。しかし多くの中には、文字にして、かつその心を伝えられる田植え歌もあるかも知れず、今後の収拾の課題といたします。
 22.6.5 埼玉県志木市
22.6.5 埼玉県志木市 22.6.1 東京都清瀬市
22.6.1 東京都清瀬市