第89回 秋の気配:秋風 西風 俳句について
第89回【目次】
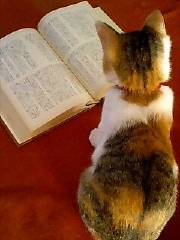
* 和歌
* 散文
* 訳詩・近現代詩
* 俳句
* みやとひたち
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市
猛暑日というのももう聞き慣れてしまいましたね。この5日には京都府京田辺市で9月としては全国の観測史上最高となる39・9度を記録しました。2000年の埼玉県熊谷市の記録を更新したものです。
立秋が来てすでに久しいのですが、日本全国さまざまに観測史の記録を更新しながら、まだ一向に涼しくなりません。
 22.8.25東京都清瀬市
22.8.25東京都清瀬市
伝統的な日本の時間感覚によれば、自然は粛々と暦に従って推移するのです。季節は二十四節気の区切り通りに進行していました。しかしこの二十四節気は、季節が日本よりおよそ一ヶ月早く来る中国華北の気候に沿って作られた方法を輸入して、そのまま使ったものです。従って、たとえば立秋が陰暦7月の始め、現行暦の8月上旬というのも、実際の気候に比べれば時期がかなり早いと感じられるのは無理もないことなのです。
秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる
立秋の頃には今日でもよく引かれる十世紀『古今和歌集』の秋歌です。言葉には表されておりませんが、この歌が詠まれた時もおそらくまだ多少暑いのです。 しかし、先んじて季節は訪れていると考えられていました。暦の上では秋になったがと思うもののそれは確認できないでいた、ふと風が来てものが音をたてる、その風に、すでに来ていたはずの秋の存在がはっきり分かってはっとした、という趣の歌です。
 22.8.24 東京都清瀬市
22.8.24 東京都清瀬市
こうして、人は身辺に季節の兆候を探すことが習わしとなり、自然の変化に敏感になり、そこに我が国独特の繊細な季節感覚が培われることにもなりました。
どの季節も空気感、すなわち風がその季節の先駆けをします。「秋来ぬと」の歌のように、秋の始まりは、言葉で言えば、風、秋風、西風でよく象徴されました。
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市
さあ、伝統的な感覚に従えばこの厳しい残暑の9月であっても秋は秋、紀貫之や藤原定家であったらこの記録的な暑い秋をどう受け容れたのでしょう。こんな秋の初めにはどんな詩歌が詠まれたことでしょうか。

2 秋風や
寺田寅彦は旧制五高、熊本高校の卒業生です。そこで夏目漱石に英語を習いました。その頃の記事です。明治30年のことです。
第二学年の学年試験の終わったころの事である。同県学生のうちで試験を
「しくじったらしい」二三人のためにそれぞれの受け持ちの先生がたの私宅
を歴訪していわゆる「点をもらう」ための運動委員が選ばれた時に、自分も
幸か不幸かその一員にされてしまった。その時に夏目先生の英語をしくじっ
たというのが自分の親類つづきの男で、それが家が貧しくて人から学資の支
給を受けていたので、もしや落第するとそれきりその支給を断たれる恐れが
あったのである。(中略)
「点をもらいに」来る生徒には断然玄関払いを食わせる先生もあったが、
夏目先生は平気で快く会ってくれた。そうして委細の泣き言の陳述を黙って
聞いてくれたが、もちろん点をくれるともくれないとも言われるはずはな
かった。とにかくこの重大な委員の使命を果たしたあとでの雑談の末に、自
分は「俳句とはいったいどんなものですか」という世にも愚劣なる質問を持
ち出した。それは、かねてから先生が俳人として有名なことを承知していた
のと、そのころ自分で俳句に対する興味がだいぶ発酵しかけていたからであ
る。その時に先生の答えたことの要領が今でもはっきりと印象に残っている。
「俳句はレトリックの煎じ詰めたものである」
「扇のかなめのような集注点を指摘し描写して、それから放散する連想の
世界を暗示するものである」
「花が散って雪のようだといったような常套な描写を月並みという」
「秋風や白木の弓につる張らんといったような句は佳い句である」
「いくらやっても俳句のできない性質の人があるし、始めからうまい人も
ある」
「夏目漱石先生の追憶」(昭和7年)
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市
失敗した試験の「点をもらう」ための運動委員とは、そんなものがあったのかと驚きますが、それはさて措き、ここで漱石が高校生向けに語った俳句についての見解はまことに興味深いものです。
私はかねがね本能的に感じるところがあって俳句からは距離を置いてまいりました。寺田寅彦の聞き書きの最後の項、「いくらやっても俳句のできない性質の人があるし、始めからうまい人もある」は、俳句に関しては(作ることに限らず俳句というものを感知できるかどうかも含めて)生来の適性があることを指摘したものと思われます。達人漱石の言葉として信を置けますが、私の本能的遠慮はおそらく間違っていなかったと、実に納得した次第です。
 22.8.28 東京都東久留米市
22.8.28 東京都東久留米市
この訪問を契機に寺田寅彦は自分自身も俳句を始め、漱石に添削を受けるようになります。長い交際の始まりでした。
 22.8.25 東京都東久留米市
22.8.25 東京都東久留米市
3 俳句と云ふもの
漱石の認めた「秋風や白木の弓につる張らん」は芭蕉の高弟向井去来の作。まさしく風を詠みこんだ秋の句です。
この句に絡んで、やはり明治の人、漱石より五歳年長の森鴎外に「俳句と云ふもの」という一文があるのを御紹介します。
俳句と云(ふ)ものを始(め)て見たのは十五六歳の時であつたと思ふ。
父と東京へ出て来て向嶋に住んでゐる所へ、母や弟妹が津和野の家を引き
払つて這入り込んで来た。その時蔵書丈〔だけ〕は売らずに持つて来たが、
歌の本では、橘守部の「心の種」、流布本の「古今集」、詩の本では「唐
詩選」があつた。俳諧の本は、誰やらが蕉門の句を集めた類題の零本で、
秋冬の部丈〔だけ〕があつた。表紙も何もなくなつてゐて、初の一枚には
立秋の句があつたのを記憶してゐる。さう云ふ本を好奇心から読み出した。
丁度進文学社と云ふ学校で独逸語を学んでゐた片手間であつた。(中略)
秋風や白木の弓に弦張らん 去来
と云ふ句がひどく気に入つて、こんな句がして見たいと思つた。その後俳
句を少しして見たが、かう云ふ向きの句は一つも出来たことがない。何事
によらず、自分の出来ない方角のものに感服してゐて、それが出来ずじま
ひになるのが、性分であるらしい。
たしかに鴎外の俳句というのはなかなか思いつきません。鴎外自身の評価は多分に謙遜だとしても、どちらかといえば俳句に適性のない方の人であったのかも知れません。
 22.8.28 東京都東久留米市
22.8.28 東京都東久留米市
漱石と鴎外とは明治の文豪の中でも偉大なだけに、何につけ違いを対比されるのが常ですが、いずれもが去来の同じ句を気に入っていたということは目を引きます。
この一文は雑誌「俳味」の明治45年(1912)1月号に初めて掲載されました。寺田寅彦が熊本高校2年生の明治30年にはまだ知られていない内容です。また、寺田寅彦の「夏目漱石先生の追憶」も「俳味」から遙かに遠い昭和7年(1932)になって書かれたものですから、どちらかがあらかじめこのことを承知していて、「そういえばこの句は佳い」と思いつくような経緯はありえません。俳句は数限りないというのにたまたま同じ一句が挙がっていたことは、何とも不思議で面白いことでした。
 22.8.21 東京都清瀬市
22.8.21 東京都清瀬市
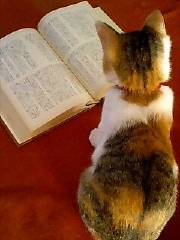
* 和歌
* 散文
* 訳詩・近現代詩
* 俳句
* みやとひたち
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市猛暑日というのももう聞き慣れてしまいましたね。この5日には京都府京田辺市で9月としては全国の観測史上最高となる39・9度を記録しました。2000年の埼玉県熊谷市の記録を更新したものです。
立秋が来てすでに久しいのですが、日本全国さまざまに観測史の記録を更新しながら、まだ一向に涼しくなりません。
 22.8.25東京都清瀬市
22.8.25東京都清瀬市伝統的な日本の時間感覚によれば、自然は粛々と暦に従って推移するのです。季節は二十四節気の区切り通りに進行していました。しかしこの二十四節気は、季節が日本よりおよそ一ヶ月早く来る中国華北の気候に沿って作られた方法を輸入して、そのまま使ったものです。従って、たとえば立秋が陰暦7月の始め、現行暦の8月上旬というのも、実際の気候に比べれば時期がかなり早いと感じられるのは無理もないことなのです。
秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる
立秋の頃には今日でもよく引かれる十世紀『古今和歌集』の秋歌です。言葉には表されておりませんが、この歌が詠まれた時もおそらくまだ多少暑いのです。 しかし、先んじて季節は訪れていると考えられていました。暦の上では秋になったがと思うもののそれは確認できないでいた、ふと風が来てものが音をたてる、その風に、すでに来ていたはずの秋の存在がはっきり分かってはっとした、という趣の歌です。
 22.8.24 東京都清瀬市
22.8.24 東京都清瀬市こうして、人は身辺に季節の兆候を探すことが習わしとなり、自然の変化に敏感になり、そこに我が国独特の繊細な季節感覚が培われることにもなりました。
どの季節も空気感、すなわち風がその季節の先駆けをします。「秋来ぬと」の歌のように、秋の始まりは、言葉で言えば、風、秋風、西風でよく象徴されました。
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市さあ、伝統的な感覚に従えばこの厳しい残暑の9月であっても秋は秋、紀貫之や藤原定家であったらこの記録的な暑い秋をどう受け容れたのでしょう。こんな秋の初めにはどんな詩歌が詠まれたことでしょうか。

2 秋風や
寺田寅彦は旧制五高、熊本高校の卒業生です。そこで夏目漱石に英語を習いました。その頃の記事です。明治30年のことです。
第二学年の学年試験の終わったころの事である。同県学生のうちで試験を
「しくじったらしい」二三人のためにそれぞれの受け持ちの先生がたの私宅
を歴訪していわゆる「点をもらう」ための運動委員が選ばれた時に、自分も
幸か不幸かその一員にされてしまった。その時に夏目先生の英語をしくじっ
たというのが自分の親類つづきの男で、それが家が貧しくて人から学資の支
給を受けていたので、もしや落第するとそれきりその支給を断たれる恐れが
あったのである。(中略)
「点をもらいに」来る生徒には断然玄関払いを食わせる先生もあったが、
夏目先生は平気で快く会ってくれた。そうして委細の泣き言の陳述を黙って
聞いてくれたが、もちろん点をくれるともくれないとも言われるはずはな
かった。とにかくこの重大な委員の使命を果たしたあとでの雑談の末に、自
分は「俳句とはいったいどんなものですか」という世にも愚劣なる質問を持
ち出した。それは、かねてから先生が俳人として有名なことを承知していた
のと、そのころ自分で俳句に対する興味がだいぶ発酵しかけていたからであ
る。その時に先生の答えたことの要領が今でもはっきりと印象に残っている。
「俳句はレトリックの煎じ詰めたものである」
「扇のかなめのような集注点を指摘し描写して、それから放散する連想の
世界を暗示するものである」
「花が散って雪のようだといったような常套な描写を月並みという」
「秋風や白木の弓につる張らんといったような句は佳い句である」
「いくらやっても俳句のできない性質の人があるし、始めからうまい人も
ある」
「夏目漱石先生の追憶」(昭和7年)
 22.8.25 東京都清瀬市
22.8.25 東京都清瀬市失敗した試験の「点をもらう」ための運動委員とは、そんなものがあったのかと驚きますが、それはさて措き、ここで漱石が高校生向けに語った俳句についての見解はまことに興味深いものです。
私はかねがね本能的に感じるところがあって俳句からは距離を置いてまいりました。寺田寅彦の聞き書きの最後の項、「いくらやっても俳句のできない性質の人があるし、始めからうまい人もある」は、俳句に関しては(作ることに限らず俳句というものを感知できるかどうかも含めて)生来の適性があることを指摘したものと思われます。達人漱石の言葉として信を置けますが、私の本能的遠慮はおそらく間違っていなかったと、実に納得した次第です。
 22.8.28 東京都東久留米市
22.8.28 東京都東久留米市この訪問を契機に寺田寅彦は自分自身も俳句を始め、漱石に添削を受けるようになります。長い交際の始まりでした。
 22.8.25 東京都東久留米市
22.8.25 東京都東久留米市3 俳句と云ふもの
漱石の認めた「秋風や白木の弓につる張らん」は芭蕉の高弟向井去来の作。まさしく風を詠みこんだ秋の句です。
この句に絡んで、やはり明治の人、漱石より五歳年長の森鴎外に「俳句と云ふもの」という一文があるのを御紹介します。
俳句と云(ふ)ものを始(め)て見たのは十五六歳の時であつたと思ふ。
父と東京へ出て来て向嶋に住んでゐる所へ、母や弟妹が津和野の家を引き
払つて這入り込んで来た。その時蔵書丈〔だけ〕は売らずに持つて来たが、
歌の本では、橘守部の「心の種」、流布本の「古今集」、詩の本では「唐
詩選」があつた。俳諧の本は、誰やらが蕉門の句を集めた類題の零本で、
秋冬の部丈〔だけ〕があつた。表紙も何もなくなつてゐて、初の一枚には
立秋の句があつたのを記憶してゐる。さう云ふ本を好奇心から読み出した。
丁度進文学社と云ふ学校で独逸語を学んでゐた片手間であつた。(中略)
秋風や白木の弓に弦張らん 去来
と云ふ句がひどく気に入つて、こんな句がして見たいと思つた。その後俳
句を少しして見たが、かう云ふ向きの句は一つも出来たことがない。何事
によらず、自分の出来ない方角のものに感服してゐて、それが出来ずじま
ひになるのが、性分であるらしい。
たしかに鴎外の俳句というのはなかなか思いつきません。鴎外自身の評価は多分に謙遜だとしても、どちらかといえば俳句に適性のない方の人であったのかも知れません。
 22.8.28 東京都東久留米市
22.8.28 東京都東久留米市漱石と鴎外とは明治の文豪の中でも偉大なだけに、何につけ違いを対比されるのが常ですが、いずれもが去来の同じ句を気に入っていたということは目を引きます。
この一文は雑誌「俳味」の明治45年(1912)1月号に初めて掲載されました。寺田寅彦が熊本高校2年生の明治30年にはまだ知られていない内容です。また、寺田寅彦の「夏目漱石先生の追憶」も「俳味」から遙かに遠い昭和7年(1932)になって書かれたものですから、どちらかがあらかじめこのことを承知していて、「そういえばこの句は佳い」と思いつくような経緯はありえません。俳句は数限りないというのにたまたま同じ一句が挙がっていたことは、何とも不思議で面白いことでした。
 22.8.21 東京都清瀬市
22.8.21 東京都清瀬市 【文例】 和歌