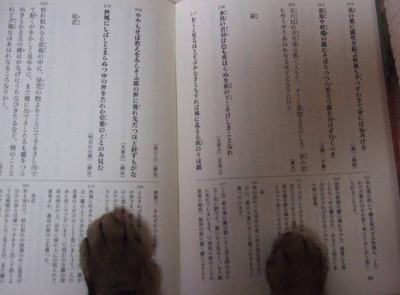第42回 初秋:朝顔・涼風・秋風・風のつま(萩)・萩・秋萩・露・白露・秋草・雁
1 七草の花(七種の花)
涼風が廻り、暦にもようやく追いつくように、あたりはいよいよ秋のたたずまいを見せてまいりました。

萩の花尾花[をばな]葛花[くずばな]瞿麦[なでしこ]の花
女郎花[をみなへし]また藤袴[ふじばかま]朝貌[あさがほ]の花
『万葉集』1538 山上憶良
この歌は一見してお分かりのとおり、短歌ではありません。『古事記』『日本書紀』の歌謡や『万葉集』などに多く見られる古代の歌体で、音節にして5・ 7・7、5・7・7の六句から成る旋頭歌(せどうか)というものです(5・7・7で成る歌体を片歌と言い、それを二つ合わせた形です。始まりは二人で片歌 一首ずつを詠み合ったものかと推定されています)。"秋の七草"とグループで秋草を捉えることは古代歌謡の時期からすでに始まっていました。
春の七草が食用の野草であるのに対して、古代から秋の七草は観賞用の花々でした。萩や尾花(ススキ)・女郎花などは今日にもその姿を知られているとお りですが、『万葉集』にアサガホと詠まれている花はおなじみのあの花ではありません。詩歌に残る花の特徴を付き合わせて、現在で言う旋花(ヒルガオ)、木 槿(ムクゲ)、また桔梗のことであるとする説などさまざまがありますが、どれも一長一短があり、いまだ決定的なものに至り着かないようです。少なくとも現 在の朝顔はそれではないと知りながら、涼しい風に揺れるこの頃の"朝顔"もいかにも初秋らしいすっきりした風情です。

2 花はいかが見るらむ
あさがほを なにはかなしと思ひけむ 人をも花はいかが見るらむ
(アサガオの花を、人はどうしてはかないものだと思っていたのだろう。
人もはかなさは同じなのに。花の方はそんな人をどのように見ている
のだろうか。) 『和漢朗詠集』294 藤原道信
『今昔物語集』(巻第二十四・三十八)によれば、この歌は内裏で何人かの貴族が「世の中のはかなき事どもを云ひて、牽牛子(あさがほ)の花を見ると云 ふ心」を詠み合ったときの歌です。この歌に先立つ10世紀の人、源順の歌に、「世の中を何にたとへむ夕露もまたで消えぬるあさがほの花」などとも詠まれま した。一日の一時だけ咲いて萎んでしまう"アサガホ"は、はかないもののわかりやすいたとえだったのでしょう。人も同じだと匂わせるところまではありがち な展開ですが、この歌はそこから更に花は人をどう見ているかと思いを廻らしているところが独自です。
確かに、人も一生、花も一生、それぞれの生き物ごとの同じ一生に違いありません。

作者藤原道信は藤原公任や清少納言などと同じ一条天皇の時代の人で、『紫式部日記』にも名前が見えます。『今昔物語集』はこの人を「形、有様より始め て、心ばへいとをかしくて、和歌をなむ微妙(めでた)く詠みける(顔かたち、たたずまいから始まって人柄もたいそうすばらしくて、和歌を見事に詠んだ)」 と解説しています。父為光が亡くなって一年が過ぎ、喪が明ける時の歌「限りあればけふぬぎすてつ ふぢ衣(=喪服)果てなきものは涙なりけり」は真率な悲しみを伝えて今日まで残る名歌です。

3 萩の花散る野辺を
さて、秋は風から始まり草木や動物に至ります。陰暦の8月過ぎ(ちょうど今頃です)に吹く涼しい北風を、伊豆のあたりで"雁渡し"と呼ぶ地域があるそ うです。北国から雁を乗せて吹いてくるというイメージでしょうか。渡り鳥である雁の姿を見ることが、伊豆地方に限らずこの国では長らく秋の到来を実感する ことでありました。早く秋が来てほしいと望むときに、雁に早く飛んで来るようにと頼む歌が詠まれたりしています。雁が来る頃、野にはまず秋の七草の萩が咲 きこぼれます。

細いしなやかな枝に咲く小さな花は散りやすく、花のそばを通れば
露しげき小萩が原に立ちよれば花摺り衣着ぬ人ぞなき
(露の深小萩の原を行けば、萩にまつわれて、誰もが花摺りの衣を着たような
姿になることですよ) 『四条宮下野集』72
などとあるように、細かな花びらが衣服にまつわることが、歌には好んで詠まれました。萩は屋敷の庭先にも植えられてありましたが、本来繁る秋草に混じって野原にあるものでした。萩の花が着物に付くのは野歩きの跡を示したのです。
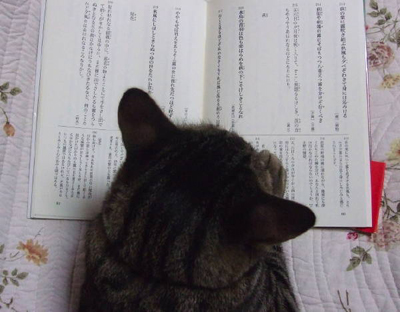
萩の歌で印象深いものに『古今和歌集』にある秋の歌があります。
萩が花散るらむ小野の露霜に濡れてを行[ゆ]かん 小夜[さよ]はふくとも
(今頃は萩の花が散っているだろう野原を、夜の露に濡れてもあの人の所へ
行こう。夜は更けるとしても) 『古今和歌集』224 詠み人知らず
これは恋人のもとへ行こうとする男性の歌です。第四句「濡れてを行かん」の「を」は強調のために入った格助詞です。夜更けの秋の野にはすっかり冷たい 露が下りています。濡れることは分かっている。濡れても構わない、それでも行こうという強い意志を「を」が表しています。
相手の女性から見てなんと嬉しい歌でしょう。何よりよいのは、暗い夜更けの野原に出で立つ彼自身が実に生き生きと幸福そうなことです。恋をして、相手にもそれが大いなる幸せであると分かるような恋が、本当に幸せな恋なのだと思えます。
秋草を分け、萩の花散る野辺を行くうちには、他の歌によくあるように、この人の着物にも細かな萩の花びらが無数にまつわり、恋人の家に着く頃は、ちょうどそのような柄に染めた模様のようになっていたかもしれない、とこの先が自然に想像される歌です。
それにしても、『古今和歌集』はこれを「秋」の巻に取り、恋歌に入れませんでした。このあたりに『古今和歌集』のプログラムの秘密があるのだろうと思 います。『古今和歌集』では季節の歌が四季を追って配列されているように、恋の歌も連続した巧妙なストーリーをもって展開します。王朝風の恋愛観によるそ のストーリーのどの場面にも、この詠み人知らずの恋歌はあまりに素直に幸福すぎて、入る場所が見つからないような気がするからです。
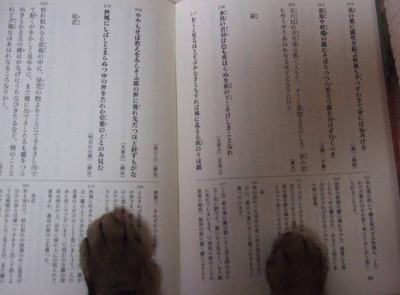
涼風が廻り、暦にもようやく追いつくように、あたりはいよいよ秋のたたずまいを見せてまいりました。

20.9.13 東京都清瀬市
萩の花尾花[をばな]葛花[くずばな]瞿麦[なでしこ]の花
女郎花[をみなへし]また藤袴[ふじばかま]朝貌[あさがほ]の花
『万葉集』1538 山上憶良
この歌は一見してお分かりのとおり、短歌ではありません。『古事記』『日本書紀』の歌謡や『万葉集』などに多く見られる古代の歌体で、音節にして5・ 7・7、5・7・7の六句から成る旋頭歌(せどうか)というものです(5・7・7で成る歌体を片歌と言い、それを二つ合わせた形です。始まりは二人で片歌 一首ずつを詠み合ったものかと推定されています)。"秋の七草"とグループで秋草を捉えることは古代歌謡の時期からすでに始まっていました。
春の七草が食用の野草であるのに対して、古代から秋の七草は観賞用の花々でした。萩や尾花(ススキ)・女郎花などは今日にもその姿を知られているとお りですが、『万葉集』にアサガホと詠まれている花はおなじみのあの花ではありません。詩歌に残る花の特徴を付き合わせて、現在で言う旋花(ヒルガオ)、木 槿(ムクゲ)、また桔梗のことであるとする説などさまざまがありますが、どれも一長一短があり、いまだ決定的なものに至り着かないようです。少なくとも現 在の朝顔はそれではないと知りながら、涼しい風に揺れるこの頃の"朝顔"もいかにも初秋らしいすっきりした風情です。

現在の"アサガオ" 20.9.13 東京都清瀬市
2 花はいかが見るらむ
あさがほを なにはかなしと思ひけむ 人をも花はいかが見るらむ
(アサガオの花を、人はどうしてはかないものだと思っていたのだろう。
人もはかなさは同じなのに。花の方はそんな人をどのように見ている
のだろうか。) 『和漢朗詠集』294 藤原道信
『今昔物語集』(巻第二十四・三十八)によれば、この歌は内裏で何人かの貴族が「世の中のはかなき事どもを云ひて、牽牛子(あさがほ)の花を見ると云 ふ心」を詠み合ったときの歌です。この歌に先立つ10世紀の人、源順の歌に、「世の中を何にたとへむ夕露もまたで消えぬるあさがほの花」などとも詠まれま した。一日の一時だけ咲いて萎んでしまう"アサガホ"は、はかないもののわかりやすいたとえだったのでしょう。人も同じだと匂わせるところまではありがち な展開ですが、この歌はそこから更に花は人をどう見ているかと思いを廻らしているところが独自です。
確かに、人も一生、花も一生、それぞれの生き物ごとの同じ一生に違いありません。

20.9.13 東京都清瀬市
作者藤原道信は藤原公任や清少納言などと同じ一条天皇の時代の人で、『紫式部日記』にも名前が見えます。『今昔物語集』はこの人を「形、有様より始め て、心ばへいとをかしくて、和歌をなむ微妙(めでた)く詠みける(顔かたち、たたずまいから始まって人柄もたいそうすばらしくて、和歌を見事に詠んだ)」 と解説しています。父為光が亡くなって一年が過ぎ、喪が明ける時の歌「限りあればけふぬぎすてつ ふぢ衣(=喪服)果てなきものは涙なりけり」は真率な悲しみを伝えて今日まで残る名歌です。

20.9.12 東京都清瀬市
3 萩の花散る野辺を
さて、秋は風から始まり草木や動物に至ります。陰暦の8月過ぎ(ちょうど今頃です)に吹く涼しい北風を、伊豆のあたりで"雁渡し"と呼ぶ地域があるそ うです。北国から雁を乗せて吹いてくるというイメージでしょうか。渡り鳥である雁の姿を見ることが、伊豆地方に限らずこの国では長らく秋の到来を実感する ことでありました。早く秋が来てほしいと望むときに、雁に早く飛んで来るようにと頼む歌が詠まれたりしています。雁が来る頃、野にはまず秋の七草の萩が咲 きこぼれます。

20.9.11 東京都清瀬市
細いしなやかな枝に咲く小さな花は散りやすく、花のそばを通れば
露しげき小萩が原に立ちよれば花摺り衣着ぬ人ぞなき
(露の深小萩の原を行けば、萩にまつわれて、誰もが花摺りの衣を着たような
姿になることですよ) 『四条宮下野集』72
などとあるように、細かな花びらが衣服にまつわることが、歌には好んで詠まれました。萩は屋敷の庭先にも植えられてありましたが、本来繁る秋草に混じって野原にあるものでした。萩の花が着物に付くのは野歩きの跡を示したのです。
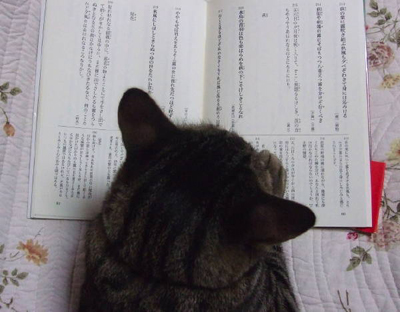
萩の歌で印象深いものに『古今和歌集』にある秋の歌があります。
萩が花散るらむ小野の露霜に濡れてを行[ゆ]かん 小夜[さよ]はふくとも
(今頃は萩の花が散っているだろう野原を、夜の露に濡れてもあの人の所へ
行こう。夜は更けるとしても) 『古今和歌集』224 詠み人知らず
これは恋人のもとへ行こうとする男性の歌です。第四句「濡れてを行かん」の「を」は強調のために入った格助詞です。夜更けの秋の野にはすっかり冷たい 露が下りています。濡れることは分かっている。濡れても構わない、それでも行こうという強い意志を「を」が表しています。
相手の女性から見てなんと嬉しい歌でしょう。何よりよいのは、暗い夜更けの野原に出で立つ彼自身が実に生き生きと幸福そうなことです。恋をして、相手にもそれが大いなる幸せであると分かるような恋が、本当に幸せな恋なのだと思えます。
秋草を分け、萩の花散る野辺を行くうちには、他の歌によくあるように、この人の着物にも細かな萩の花びらが無数にまつわり、恋人の家に着く頃は、ちょうどそのような柄に染めた模様のようになっていたかもしれない、とこの先が自然に想像される歌です。
それにしても、『古今和歌集』はこれを「秋」の巻に取り、恋歌に入れませんでした。このあたりに『古今和歌集』のプログラムの秘密があるのだろうと思 います。『古今和歌集』では季節の歌が四季を追って配列されているように、恋の歌も連続した巧妙なストーリーをもって展開します。王朝風の恋愛観によるそ のストーリーのどの場面にも、この詠み人知らずの恋歌はあまりに素直に幸福すぎて、入る場所が見つからないような気がするからです。