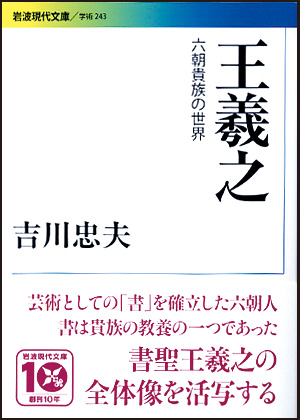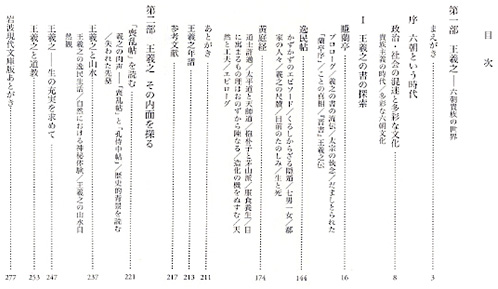吉川忠夫『王羲之』岩波現代文庫(2010)

人間王羲之の実像が浮かび上がる
今回から書と文字についての本を取り上げます。書を幅広いものとして捉え、学ぶうえで新旧の必読書を紹介します。さて、東京国立博物館の「王羲之展」はご覧になったでしょうか。
甲骨文字から始まって碑学派まで、王羲之のみの展示ではありませんでしたが、王羲之を理解するには、中国書道史全体を見る必要があるのです。甲骨文の発生(紀元前15世紀)から始まる書の歴史は、大きく二つに分けられます。一つは中国の漢字の書体がさまざまに変化発展した時代、最後の書体である楷書が成立した3世紀までの「書体史」で、二つめが書の「美しさ」
が大きな価値として自覚され、さまざまな書風が展開する「書道史」です。その節目の時代に王羲之は生きたのです。それが展覧会のキャッチフレーズ「書を芸術にした男」の意味です。
◎
さて、王羲之が「書を芸術にした男」であり、「書聖」と崇められているからといって、その人間像がすっきり と納得できるわけではありません。むしろ王羲之の場合、彼自身の真蹟が一点も残っていないことともあいまって、実際の王羲之その人がどんな人間であったのかは茫漠としてしまいます。
吉川忠夫『王羲之』は1972年に刊行された本ですが、最近文庫になり、手軽に読むことができます。著者の吉川氏は京都大学の中国学の伝統を受け継いでいる方で、おもに魏晋南北朝時代の宗教史が専門です。
この本は王羲之の書の技術的や書道史上の位置を解説した本ではありません。また専門の宗教史の研究書でもありません。王羲之の実像にさまざまな角度から光を当てようとする試みです。文章は簡潔で非常に読みやすく、中国史に通じていなくとも抵抗なく入っていけると思います。
手がかりになるのは彼の生きた時代です。序文の「六朝という時代」にはこうあります。「六朝の文化ははなはだ異彩を放った……それまで儒教に従属されていたもろもろの文化現象 が、それぞれ独自の存在たることを要求し、獲得する。……書画をはじめとする諸芸術が、勧善懲悪的な倫理から解放され、それ自体の美が追究されることになった」。この思潮が王羲之の書の背景にあったのです。
もうひとつの手がかりは「十七帖」をはじめとする彼の書簡です。これによって、王羲之が 我々と同じような感情生活を送っていたと考えることはできないものの、我々にも理解できる等身大の人間として迫ってくるのです。第3章の「いかに生きるべ きか」は、エピソードや書簡から彼の生活・信仰・思想を再現しようとする本書のもっとも面白い部分ですが、たとえば吉川氏は、彼の書簡に再三登場する「目前」という言葉に注目しています。この「目前」は単なる現在の瞬間という意味とは異なって、「楽しみがいつ悲しみに変わるかもしれない不安におびやかされ」たものであり、それが王羲之の思想のキーワードになっているとしています。
こうした彼を取り巻く時代の流れやもろもろの状況、それに対する彼の態度が彼の書に影響しないとは考えにくいでしょう。第2章では彼が赴任していた地方の緊迫した状況と彼の書の関係にも触れられています。吉川氏は 「……王羲之を取り巻く喫緊の状況がかれの心を張りつめた糸のごとく緊張させ、その緊張が必ずや書の上にも反映され」ているのではないかと書いています。
ここに紹介した部分だけでも、王羲之の書がそれまでとはなんだか変わって感じられてこないでしょうか。表現された書と人間像との関係は一筋縄ではいきませんが、書をトータルに理解するためには、さまざまな入口があることを実感させられます。この本は王羲之だけではなく、中国の書を理解するためにも最上の案内図だと思います。
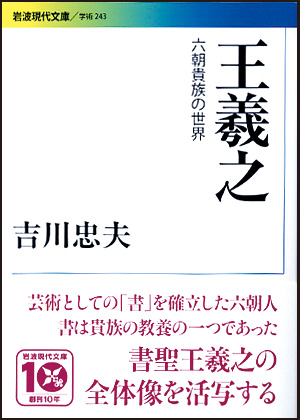
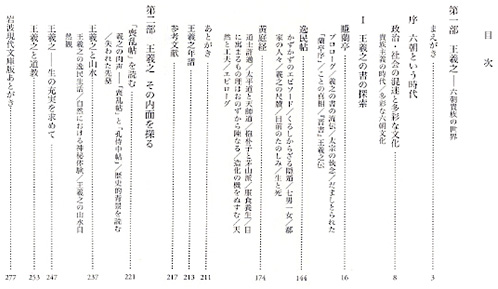
◎
さて、王羲之が「書を芸術にした男」であり、「書聖」と崇められているからといって、その人間像がすっきり と納得できるわけではありません。むしろ王羲之の場合、彼自身の真蹟が一点も残っていないことともあいまって、実際の王羲之その人がどんな人間であったのかは茫漠としてしまいます。
吉川忠夫『王羲之』は1972年に刊行された本ですが、最近文庫になり、手軽に読むことができます。著者の吉川氏は京都大学の中国学の伝統を受け継いでいる方で、おもに魏晋南北朝時代の宗教史が専門です。
この本は王羲之の書の技術的や書道史上の位置を解説した本ではありません。また専門の宗教史の研究書でもありません。王羲之の実像にさまざまな角度から光を当てようとする試みです。文章は簡潔で非常に読みやすく、中国史に通じていなくとも抵抗なく入っていけると思います。
手がかりになるのは彼の生きた時代です。序文の「六朝という時代」にはこうあります。「六朝の文化ははなはだ異彩を放った……それまで儒教に従属されていたもろもろの文化現象 が、それぞれ独自の存在たることを要求し、獲得する。……書画をはじめとする諸芸術が、勧善懲悪的な倫理から解放され、それ自体の美が追究されることになった」。この思潮が王羲之の書の背景にあったのです。
もうひとつの手がかりは「十七帖」をはじめとする彼の書簡です。これによって、王羲之が 我々と同じような感情生活を送っていたと考えることはできないものの、我々にも理解できる等身大の人間として迫ってくるのです。第3章の「いかに生きるべ きか」は、エピソードや書簡から彼の生活・信仰・思想を再現しようとする本書のもっとも面白い部分ですが、たとえば吉川氏は、彼の書簡に再三登場する「目前」という言葉に注目しています。この「目前」は単なる現在の瞬間という意味とは異なって、「楽しみがいつ悲しみに変わるかもしれない不安におびやかされ」たものであり、それが王羲之の思想のキーワードになっているとしています。
こうした彼を取り巻く時代の流れやもろもろの状況、それに対する彼の態度が彼の書に影響しないとは考えにくいでしょう。第2章では彼が赴任していた地方の緊迫した状況と彼の書の関係にも触れられています。吉川氏は 「……王羲之を取り巻く喫緊の状況がかれの心を張りつめた糸のごとく緊張させ、その緊張が必ずや書の上にも反映され」ているのではないかと書いています。
ここに紹介した部分だけでも、王羲之の書がそれまでとはなんだか変わって感じられてこないでしょうか。表現された書と人間像との関係は一筋縄ではいきませんが、書をトータルに理解するためには、さまざまな入口があることを実感させられます。この本は王羲之だけではなく、中国の書を理解するためにも最上の案内図だと思います。