現代書道の父
比田井天来
天来が遺していったもの
比田井和子
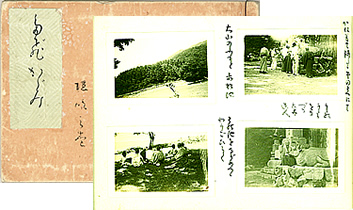 ここに一枚の写真がある。杖をつき、鋳物の牛の頭をなでながら茶目っ気たっぷりのポーズをとっているのは比田井天来、そして撮影したのは、天来の妻、小琴である。昭和十一年、島根県大山へ登ったときのスナップ写真だ。
ここに一枚の写真がある。杖をつき、鋳物の牛の頭をなでながら茶目っ気たっぷりのポーズをとっているのは比田井天来、そして撮影したのは、天来の妻、小琴である。昭和十一年、島根県大山へ登ったときのスナップ写真だ。
夫に随行して旅をする小琴の旅装の中には、一台の小型カメラが入っていた。写真撮影を教えたのは長男厚である。厚はNHKに勤務していたが、昭和十年に病気になり、死亡した。二十七歳の若さだった。才能に恵まれ、将来を託していた息子の突然の死。小琴にとって写真を撮ることは、厚への供養でもあった。汽車から見た風景や道端に咲く花、しらかばを、小琴はカメラに収めた。
同年八月一日から、小琴は夫に随行して、福井から神戸をまわった。このときも、カメラを携えていた。直江津、唐尋坊、人丸神社、六甲山。風景や同行した人々を、カメラは記録した。
旅が終わり、小琴は小さいノートを作ってこれらを貼りこんだ。旅先で詠んだ短歌や感想も書き込んだ。これが「たびかゞみ」と題された旅行記である。
厚の供養のために始めた撮影に、小琴は次第に魅せられていく。船の上から見た島影や朝日に輝く海面、波しぶき、夕映えの山々などが、モノクロームの美しい世界を作りあげている。そしてもちろん、夫、天来の姿もカメラにおさめられた。山高帽をかぶって阿蘇の火口付近にたたずむ姿や、釣り糸をたれている後姿など、もっとも身近にいる妻ならではの貴重な記録である。
四冊残されている「たびかゞみ」は、昭和十年と十一年の旅を記録している。「一の巻」では福井・神戸・明石、「二の巻」では会津から東北、仙台・静岡・神戸・別府・熊本、「北海道の巻」は秋田から青森・函館・旭川・札幌・小樽、「隠岐の巻」は埼玉から松江・隠岐と、きわめて広い範囲にわたっている。そして、旅はこの二年間に限られるものではなかった。
昭和十一年、隠岐へ向かう船の中で、小琴は夫天来に夜半一人、部屋に取り残される。窓から眺める暗い荒れた海の風景。その時に詠んだ小琴の歌「さびしさにたへえぬわれとしらねばやひとりしおきてゆきますわがせ」。それは、一人孤独に芸術世界を切り拓こうとする夫天来を思い遣る歌でもあった。
天来は、その生涯の多くを地方への旅にあてた。四十二歳の出雲遊歴から六十五歳の隠岐旅行まで、ほとんど毎年のように旅に出た。しかも北は北海道、樺太から南は九州、台湾まで、不自由な交通事情の中、実に精力的に旅をした。
最初の遊歴は大正二年、出雲だった。このときの新聞記事が残されているが、揮毫の注文が殺到し、大成功だったことがわかる。天来は、地方で作品を頒布するにあたり、自作を写真に撮ってパンフレットを作っていたので、当時の作品を見ることができる。この年の作品には、師、日下部鳴鶴の影響が顕著である。
二回目の出雲遊歴は三年後、大正五年だった。このときに助手をした井原自琢の証言にもあるように、作品は三年前とはまったく変っていた。鳴鶴の影響は消え、独自の筆法が生れている。「人が見ていたほうが愉快に書ける」と豪語した天来の書は、見知らぬ土地で、見知らぬ人々の眼にさらされながら、変貌を遂げていった。(詳細は筆者著「それは旅から始まった」『現代書の誕生』天来書院刊を参照)
これ以降、天来は毎年のように地方遊歴の旅に出た。大正六年は九州、八年は松江から戻った後北海道全道をまわり、弘前へ寄って年末に帰宅、九年は山形、秋田、松江、京都、新潟、金沢、十年は豊橋、静岡と、旺盛な行動力を見せている。
大正九年、天来は故郷の友人に宛てて、こんな手紙を送った。
当地の書道界では、順に古老が凋落し、虚に乗じて盲目の寺子屋連中や無学の富豪、飢銭の学者たちが巧みに操縦して、向上している書道界を逆転させようと企てています。
小生は前面に立ち、反対していますが、俗事によって多忙を極め、閉口しています。営利会社の重役になったようです。多数の役員たちは、一度地位を去ったら二度と役職を得られないので、小生などの意見に賛同する人はきわめて少数で、気の毒でもあり、あまり憎むこともできません。小生は総務を辞任し、ようやく小閑を得ました。
地方の新進書家が真面目に研究しようとしている矢先、中央が凋落していることは、まことに痛心の極みであります。
書壇に属さず、書斎にこもることもせず、天来は地方への旅を続けた。そして書の古典の重要性を説き、講習会をし、作品を頒布し続けた。そして生涯の間、止まることなく、天来の作品は新たな世界を拓き続けた。
この遊歴には一つの目的があった。それは、古今の書道古典を展示し、誰でも見ることのできる博物館「書学院」の建設である。
大正七年、天来は「書道館建設辞」を書いた。この「書道館」は「書学院」と改められ、翌年「書学院建設趣旨書」が発表された。少し長いが、全文を引用する。原文は漢字とカタカナであるが、読みやすいようにひらがなに直し、一部漢字をかなに変えた。
書学院建設趣旨書
書道の東洋に重んぜられしこと由来久し。文章詩歌と共に事を記し言を伝うるの要道たるは固より言をまたず。その高尚なる者にいたりては、作者の性情が芸術的に美化せられて、点画使転の間に活躍し、観者の性情と共鳴して、之に美妙なる感興を与え、又は観者の性情を喚起して之を高遠なる妙境に導き、人をして塵外に超然たらしむ。観る者すでにかくのごとし。いわんや自らこれを修め、これを学ぶ者においてをや。その性情がいかに霊妙なる暗示を得て、又いかに偉大なる感化をうくるかは、少しく固中の消息を解する者あらば、必ずやこれを首肯するに吝かならざるべし。
維新の初め、文華煥発書道勃興の兆しあり。幾くもなくして欧米文化の輸入は、さらにより以上に焦眉の急を告げたり。一時書道の衰退せる、また勢いのやむをえざる所なり。東洋文化の源流は支那古代に起り、殷周に盛んに唐に極まり、爾来逓下して今日に及べり。書道もおおむねその数をもれず。わが朝昔日の文化は李唐に負うところのもの甚だ多し。書道においても作家また乏しからず。その後国交杜絶衰軌を異にし、宋元の影響はわずかに釈氏及び儒家の一部に止まる。明末清李の交通ようやく繁く、碑帖旧拓の精、墓誌新出の珍、舶載遺すなく、金石文字の学、また民国に輸せず。
今や帝国の余威は四表に楊り、東洋文明の中心はまさに我においてその機軸を転ぜんとす。この時に当り、蔚然として書道の勃興を見る、あに偶然ならんや。よろしく当に内外古今の名蹟を集めて一堂に展開し、長を取り短を補い、天下の臨池家と商略凝議互いに相研鑚して、先哲の往規を窮め、将来の器識を導き、もって東洋文化の中枢たるに慙じざるを期すべし。
由来書道の荒替せし所以を尋ぬるに、その原因凡そにあり。一はすなわち人智小慧に趨き、誠意欠如して浮華年に加うるに因り、一はすなわち師承伝なく、俗匠帷を下し、蒙を愚にし智を塞ぎ、これを細流小派に情繁して、書道の大海に遊泳せしめざるに因る。書道の大海とはすなわち何ぞや。いわく、歴代大家の碑版法帖すなわちこれなり。抑も学問芸術に流派を論じて、いたずらに党同伐異を事とするの徒は、皆いまだその堂奥に達せざる者なり。甚だしいかな、流派のわが文芸を禍するや。歴代逓下の源委いまだかつてこれに存ぜずんばあらざるなり。よろしく従来の弊風を打破して、書道研究の一代革新を図り、学者をしてあまねく書道の沿革を識り、歴代大家の劇跡を閲覧して、各々性に適する所に従い、自由に法帖碑版を選択して、学習するの便宜を得しめ、兼ねて一般的書道趣味の向上を規画すべし。わが大和民族は、まさに地に委せんとする東洋古代の文化の保護者として立たざるべからざる使命を有せり。ゆえに東洋芸術の精華たる書道の保芸者として立たざるべからざるなり。これ吾輩が書学院建設の急務を絶叫し、これがためにあらゆる努力を貢献して、なおかつ辞せざらんとする所以なり。四方の君子、幸いに吾人の微衷を諒とし、書道研究上一大革新を図るの機、早からしめば、あにただに道人の感謝惜しく能わざる所なるのみならんや。
大正八年 七月十五日 天来道人 比田井 象之誌
犬養毅、男爵細川潤次朗、頭山満、大谷光瑞、伯爵樺山資紀、嘉納治五郎、日下部東作、公爵松方正義、伯爵松平直亮、股野琢、男爵後藤新平、小牧昌業、沢柳政太郎、三島毅、釈宗演、伯爵土方久元、国外粛親王
維新以後、明治政府による廃仏毀釈や「鹿鳴館」に代表されるような急速な西洋文化の導入によって、東洋文化は衰退の危機に陥っていた。天来がこの「趣旨書」を書いた当時、欧米の帝国主義列強がアジアに進出し、そして大日本帝国も列強に対抗して、「富国強兵」「国外膨張」政策を取る中で、アジア諸国の人々は自国の歴史や文化に覚醒しつつあった。急激な西欧化に対し、芸術界では、たとえば、岡倉天心が日本美術の芸術としての独自性を訴え、また、「アジアは一つ」と主張して、西欧文明と異なる文化的卓越性を証明しようとした。書道は、東洋と日本の文化、および人々の精神性を形成している、いわばアジア的なるものの中心をなしている、と天来は考えた。明治期の浅薄な「脱亜入欧」の風潮のさなかに、日本人の精神性の基盤となる「東洋的なもの」「東洋文化」の再興を図る天来がいる。そして、その東洋文化の衰退に拍車をかけているのが、保身のために狭量な分派活動を行っている中央の書道界であった。
このような文化の急激な西欧化に対する危機感と、東洋精神の再興に賛同したのが、歴代の首相をはじめとした文人的政治家たちと、アジア主義的な伝統派たちであった。そして、さらには西洋文化に伍する日本伝統文化を普遍化しようとする文化的改革者、開拓者たちであった。
犬養毅から天来への書簡はたくさん残っているが、大正七年七月十日の書簡には、書道館に関する記述がある。
敬啓 書道館之件、至極御同感に候間、若し御用あらば御申越可被下候。微力を尽し可申候。
高作は時々拝見候得共、御恵寄之拓本にて篆隷并仮名拝見、敬服致候。乍序祝暑安候。不一。
七月十日 犬養毅
天来大兄梧右
書道館(後の書学院)建設についてはまったく同感です。ご用があればおっしゃってください。微力を尽くします。作品は時々拝見していますが、いただいた拓本で篆書隷書仮名を拝見し、敬服しました。
また、天来が台湾へ行くときの推薦状も残っている。「友人、比田井天来君をご紹介します。同君は書道をもって台湾を漫遊するはずですので、相当の人にご紹介ください。」心のこもった推薦状である。
犬養毅は昭和五年初秋、代々木書学院を訪れた。歓談のあと、天来と犬養毅は連れ立って代々木練兵場を散策したが、このとき、銀行家、柳井寒泉氏が十六ミリ映画を撮影した。天来を撮影した、唯一の貴重な動く映像である。(ビデオ『比田井天来の生涯』天来書院刊に収録)
二度、首相を務めた松方正義も天来と極めて親しかった。天来の長女、ゆり子(抱琴)が、手記を残しているのでご紹介しよう。
年代ははっきり覚えていないが、大正四・五年くらいであろうか。鎌倉大町琵琶小路に住んでいた頃のことである。父はやはり鎌倉に住んでおられた松方正義公爵と親交があった。
松方さんはご老齢であったし、父は若かったので、年齢から言うと親子くらいの違いがあったかもしれない。松方さんは非常に書が好きであったので、父から書の話を聞くのを喜ばれた。時折散歩のついでに家の前へ来られ「比田井君、夕食食いに来ませんか」と誘われた。
ある夕方、父はよそいきの着物に着替えていた。(父は着物を着替えることが嫌いで、どこへでも普段着のまま出かけてしまう。寝巻きのままで外出してしまうことさえあるので、母がいつも困っていた。そんなわけで、父が着物を着替えていると、家ではちょっと目立ったのである)
私が「どこへ行くの」と聞いたところ、「松方さんへ」といったが、袴のひもをしめながら、うれしさを包み隠せない様子であった。私はこのときくらい、父が子どものようにかわいらしく見えたことはない。ご馳走になりながら、尊敬する年長者に大好きな書のお話をするのは、どんなに楽しいことであったろうか。
松方さんが亡くなられてから、形見の羽織をいただいた。着物にとんちゃくしない父であったが、時折母に「松方さんにいただいた羽織を出してくれ」と言っては、着て出かけた。お形見の羽織を着て、松方さんをなつかしんでいるようであった。
天来は、陸軍幼年学校習字科で教えた後、大正四年から八年までの間、東京高等師範学校講師をつとめた。講道館柔道創始者、嘉納治五郎との交流はこのときからのものだと思われる。
図は大正五年、嘉納治五郎から天来宛の書簡である。本のトビラの揮毫を天来に依頼し、天来はさっそくしたためて嘉納に届けたようだ。依頼されたのは三枚、すべて隷書で書いたらしい。これに対して嘉納は、最初の一枚は隷書でよいが、残りの二枚は書体を変えて楷書で書いてみて欲しいと注文をつけている。遠慮のない交流のさまがうかがえる。
失脚の後、大正八年に朝鮮総督となった斉藤実との交流は、書籍として結実した。激しい反日運動を経て、明治四十三年(1910)韓国併合の後、朝鮮文化の掃討がなされる中で、顧みられぬ李王朝の書道に芸術の真価を認めて、天来が編集、発行した「朝鮮書道精華」全五巻である。それは、柳宗悦が朝鮮の芸術文化に注目したのと同時期であった。
前年私が朝鮮に遊んだ時、古本屋の紙くず同様に積み上げてある中から立派な筆跡の尺牘を見つけ出して、これを調べてみると日本の豊臣時代前後にあたるもので、日本人の書はずっと堕落しているのに、古意の多いのに驚きました。それが一人や二人ではない。幾人も上手な人があります。市場で買うことのできるものは全部買いましたが、そのかわり本屋が値を上げてきたのには困りました。それからだんだん欲が出てまいりまして、李王家のお蔵にある古文書が見たくなり、李王職のゆるしを得て、李王家の宝蔵から同博物館、総督府の博物館、その他個人の所蔵にいたるまで写真師を連れてくまなく探し回り、書として私の目についた善いものはことごとく撮影いたしました。
数年前から、斉藤総督のご好意により、編集ができればすぐにも出版できるように材料は整っておりましたが、私が忙しいのでのびのびになっておりました所、このたびまた総督のご好意で、金敦熙と申す朝鮮第一の書の先生を手伝いによこしてくださることになっておりますから、遠からず朝鮮人の書の尺牘を、読めるように釈文をつけて発表することにいたします。尺牘の字は、一般の人が今まで見ている気抜けビールのような書ではありません。(比田井天来「書道春秋」より)
「朝鮮書道精華」には、新羅の金生から始まり、六十名の作品が掲載されている。斉藤実は封面を揮毫し、発行されるや、さっそく注文する手紙を送った。
このような筆跡は、戦乱が続いた本国ではほとんど失われてしまったという。書道史の空白を埋める貴重な書籍である。
東京青山墓地に、天来が揮毫した浜口雄幸の墓がある。ライオン宰相の異名をとった浜口は、昭和五年にピストルで撃たれ、その傷がもとになって翌年死亡した。犬養毅は昭和七年、五・一五事件で射殺された。そして斉藤実もまた、昭和十二年、二・二六事件で凶弾に倒れた。
天来を愛し、援助を惜しまなかった文化人たちの死。彼らと共にはぐくみ、守ろうとしてきた東洋の叡智を、こなごなに打ち砕こうとする不穏な動き。徒党を組んで勢力争いを繰りかえし、保身に徹して、書を貶めている中央書壇。
天来は行動をおこさざるを得なかったのではないだろうか。
昭和十二年一月、天来は大日本書道院を創設し、総務長となった。
かつて「書学院建設趣旨書」で、「甚だしいかな、流派のわが文芸を禍するや」と、流派を激しく排斥した天来は、公募展の開催にあたっても、この態度を貫いた。同年八月に上野公園美術館で開催された第一回大日本書道院展では、天来の単独審査が敢行されたのである。
審査員のことも種々考えてみたが、いく組かの科を分ち、その一科の単独審査であれば、主義の違うものは他の審査科で採ってくれればよいから、自分の主義に合する作品のみを採り、自分の鑑識で悪いと観るものはどしどし落選させることができるから、自分の理想を忌憚なく実現することができるけれども、全会を一人の単独審査とする場合には、各流派の出品があれば、日本の書道を背負って立つ責任があるので、自分の鑑識はいかに正しいと信じていても、現代人の常識的に重きを措いている流派の書は、相当な地位に置かなければならぬようなことになりがちであるゆえ、いたずらに責任のみが大きくなり、自分の理想はかえっておこなわれなくなるから、たとい二三人でも相当の審査員を得て、第一回から科を分つ単独審査制にしたいと考えてみたが、これまた波乱を起こすおそれがある。なんとなれば知名の専門家は何れかの既成団体に関係があるから、いずれかの団体中より引き抜かなければ人がないから、やむことを得ず、二ヵ年の準備期間中は、道人の単独審査ということにして発表したのである。(『書勢』第一巻四号)
公募展で平等な審査をするのは不可能に近い。流派の代表である審査員は、自分の流派や門人に、よりよい賞を与えようとするからだ。多数決の審査では、多数の審査員を擁する流派が有利になる。審査結果は「質より量」の世界になる。しかも、多数決なのだから、責任は審査員にはない。
天来は、多数決審査という逃げ場を拒絶した。みずからの責任ですべての作品を審査した。それは、流派の精力拡大に走る書壇への、孤独な挑戦だった。
世の中のことわざに「習うより慣れろ」ということがある。このことわざは、はなはだ無意味なるばかりでなく、かえって害毒を流すおそれがある。習うということには心が付随しているが、慣れろということには心の働きがないから、慣れれば慣れるほど、心の支配を離れて機械的になるのである。この機械的になったところが、いわゆる病菌に冒されているので、これより発生するところの毒素は芸術を俗了し、代議士を党派根性にし、官吏を杓子定規にし、教員を蓄音機にし、あらゆる階級をと毒して、ついには国家を萎靡消沈の域に導くのである。ゆえに我輩はこのことわざを訂正して「慣れるより習え」と改めたいのである。(比田井天来著『書の伝統と創造』雄山閣出版刊)
天来は、師の手本を学ぶことを否定し、広く古典を学んで独自の世界を拓くことを主張したが、古典の学び方にも独特の主張があった。あらゆる古典を学べ、と主張したのである。一つの手本を学ぶと手に癖がつく。実用書を書くなら手に癖をつけたほうがよいが、芸術書を学ぶなら、癖をとらなくてはならない。つまり、一つの傾向の書を学んだ後は、これと逆の特徴をもつ書を学べと教えたのである。
また、個性を重んじるという人がいるが、生まれながらにしてもっているものが真の個性とはいいがたい。自分が個性だと思っているものは、心に巣くう虫けらかもしれない。虫けらを殺し、新たな虫をも殺し、すべての虫を殺し尽くして、はじめて真の個性がでると説いた。
天来は、慣れて惰性化することをもっとも嫌った。作り上げられた価値を踏襲するのではなく、これを破壊し、異質の要素を取り入れて新たな世界を拓くことを、天来は主張した。流派を否定し、退路を断って、孤独な道を歩みとおしたのである。
今はあまり語られないが、比田井天来が一生の仕事として精力を傾けていた事業がある。それは「漢字整理」である。
天来は大正十年から、古典の全臨集「学書筌蹄」を発行したが、このシリーズの特徴は、天来みずから碑帖解題、釈文、語注、字説を書いていることにある。臨書原本には、活字と異なった字形がひんぱんに登場するが、その変遷の過程を明らかにしようとしたのが「字説」である。書体にはその書体独自の歴史がある。一般に親しまれている活字は、実は篆書の字形を機械的に直訳して作ったもので、いたずらに複雑で書きにくい。歴史の中で、ふだん書かれてきた楷書体(筆写体)こそ書きやすい形であり、それを標準にすべきだと天来は考えていた。
その上、活字はいたずらに数が増え、複雑になってしまった。そこで、現在ほとんど使われていない漢字や、ほかの字で代用できる漢字を整理し、複雑な漢字は唐時代の書きやすい楷書体に改めようとしたのが、天来の「漢字整理」であった。漢字こそが、東洋の文化を統一する基盤となる。中国、朝鮮半島、日本の人々の文化的精神性を一つとするのは漢字である。その漢字をすべての人にとって、書きやすく美しいものに統一しようとしたのであった。
書学院に、「愚公帖」と名づけられた書類の束がいくつか残されている。王羲之や顔真卿、鄭道昭の拓本が一字ずつ切り離され、細長い紙に、字書の順に貼り付けられている。書の古典に見られる美しく書きやすい字形を集めて、漢字整理の資料にしようとしたのである。しかし、あまりに遠大なこの計画は、完成を見ずに終わった。
昭和十三年十月、癌が再発した天来は、死期が近いことを予感したのだろう。息子、南谷にこう言った。「おれが書家になったのは一生の不覚だ。書道のことはおれでなくてもやれる人はいくらでもあるが、漢字整理の仕事はほかの者には決してできるものではない。」また、あるときは、南谷を枕もとに呼び、完成まで生きられるように、成田山へ行ってお札をもらってくるように言いつけたという。
天来にとって、書は文人の遊びではなかった。それは、すべての人と共有すべき財産であり、すべての人を豊かにすべき文化であった。書道史の中で、長い年月をかけて美しく、そして書きやすく発展した漢字を、現代社会に役立てることこそが、みずからの使命であると、天来は感じていたのである。
新潟県西蒲原郡分水町大河津分水公園、悠然と流れる信濃川に向かって、その碑は建っている。石は高さ七.二七メートル、幅二.五メートル。重量は石碑が二〇トン、台石五〇トンの巨大な碑だ。
越後平野をうるおし、豊かな恵みをもたらす母なる信濃川も、大河津分水が通水するまでは、悪魔の川と恐れられていた。大洪水が堤防を破り、家を流し、田畑を破壊した。明治四十二年に着工し、十八年の歳月と一千万人の人手を要して、ようやく完成した分水の大工事を記念して建てられたのがこの「信濃川治水紀功碑」である。
書体は楷書。字数は一五〇〇字と長文だが、明快で力強い文字なので、少し離れた場所からでも読むことができる。
天来がこの碑文を書いたとき、関東大震災で自宅が倒壊したために、長野県に疎開していた。不自由な生活の中で、信濃川治水工事に邁進した人々の情熱を、天来は共に分かち持ったのであろう。これほどの量の力強い文字を書ききった精神力と情熱は驚嘆に値する。
大自然の猛威に向き合う一人一人の力は弱い。しかし、度重なる挫折や困難にもかかわらず、同じ目的を達成するため、共に力を合わせれば、いかに年月がかかろうと物事は達成できる。天来の心からのメッセージがここに込められている。
天来は現代書の父と呼ばれている。しかし、この言い方は誤解を生みやすい。現代では、書は芸術として、学問や諸文化と切り離して語られることが多いが、天来の主張はこの逆であるからだ。天来にとって、書とは漢学や文字学とともにあり、学校教育はもちろん、社会の中に明確に生きている精神文化であった。天来にとっての書とは、社会の中で生き、社会に影響を与え、社会を支える精神基盤そのものだったのである。