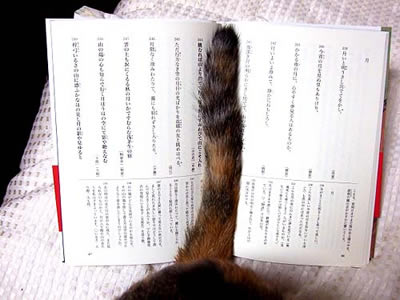みやと探す・作品に書きたい四季の言葉
連載

「泉鏡花集」を開くみや

卯の花
1 夏は来ぬ
さわやかな晴天が続いています。今年の暦では5月2日が八十八夜、5月6日が立夏でした。名実ともに初夏の季節となったのです。夏の到来といえば思い出されるのがこの歌です。
夏は来ぬ 佐々木信綱
一
卯の花の匂ふ垣根に
時鳥[ほととぎす]早も来鳴きて
忍音[しのびね]もらす夏は来ぬ
二
さみだれのそそぐ山田に
賤の女[しづのめ]が裳裾[もすそ]ぬらして
玉苗[たまなへ]植うる夏は来ぬ
*第二行「賤の女」はのちに「早乙女[さおとめ]」に改変。
三
橘[たちばな]の薫[かを]る軒端の
窓近く蛍飛びかひ
おこたり諌[いさ]むる夏は来ぬ
四
楝[あふち]ちる川[かは]べの宿の
門[かど]遠く水鶏[くゐな]声[こゑ]して
夕月[ゆふづき]すずしき夏は来ぬ
五
五月闇[さつきやみ]蛍飛びかひ
水鶏[くゐな]鳴き 卯の花咲きて
早苗[さなへ]植ゑわたす夏は来ぬ
一番から五番までを通して初夏の田園風景のさまざまを綴り、五番の歌詞はまとめのような造りになっています。季節もゆるやかに進行していて、一番はちょうど今頃の自然を歌っていますが、二番の冒頭「五月雨」はもう梅雨の雨を指します。五番にある「五月闇」とは雨曇りがちで暗いこの時期の日中の空模様をいう雅語です。五番の歌詞は、五月の夜の闇に蛍が飛ぶのではなく、うっとうしい五月闇の頃も、夕べには涼しげに蛍が飛び交い、という意匠なのだろうと思います。古典の季節帯では、夏とは立夏から立秋の前まで、現行暦に直せば5月の6、7日頃から8月の上旬までにあたります。このうち梅雨の平均日数は42日と言いますから、陰暦時代の「夏」における雨天の割合はまことに大きかったと言えます。

「夏は来ぬ」の歌詞は今日では実によく出来た古典の教材です。五番までのうちに、気象の変化も、そこに見られる伝統的な季節の動植物も、農耕作業の姿まで見通せます。卯の花、ほととぎす、橘、蛍、水鶏など、実際の姿は全く見たこともない人が今は多いことでしょう。そんな花や動物がかつてはいかにも夏を感じさせる親しい季節の景物であったことを、今でもこうした古い歌で継承することができるのは幸せです。父祖の昔の私たち日本人がどんな暮らしをし、何を見聞きし、どのように感じてきたか、感情の継承ができなくなると古典の正統な継承も難しくなることでしょう。歌い継がれて行く歌というのはそういう意味でも大切な財産です。
作詞者佐々木信綱[明治5〜昭和38(1872〜1963)]は万葉学者で歌人、明治34年(1901)に和歌の結社竹柏会を組織し、機関誌「心の花」で穏健・清新を旨とする新派和歌を推進し、落合直文の浅香社、正岡子規の根岸短歌会と、当代の三大潮流をなしました。お弟子には九条武子や柳原白蓮といった華やかな面々が列なっています。明治34年(1901)といえば、「たびかがみ」の連載(平成12年12月〜18年12月・天来書院HP)でご紹介してまいりました比田井小琴[比田井もと子・旧姓田中
明治18〜昭和23(1885〜1948)]が、終生の師となった比田井天来(比田井鴻)と結婚した年でもありました。17才の小琴(もと子)が結婚した年、日本女子大学の前身である日本女子大学校が開校し、そこに学んだ平塚雷鳥らの「青鞜」がその後の女権運動の礎となったことはあまりにも有名です。与謝野晶子が代表作「みだれ髪」を発表し、旺盛な作家活動をスタートしたのもこの明治34年でした。詩歌の世界はそれまでの作風を旧弊となして新派へ、叙情的な路線へと急展開し、「新しい女」の台頭をすぐ先に控えるこの時期に、学校教育ではなく国学者に個人的に弟子入りするという小琴の勉学はまことに珍しく、稀少な例でした。小琴が就いた阪正臣[ばんまさおみ
安政2~昭和6(1855~1931)]は明治天皇の信任のもと、当時の和歌所寄人(わかどころよりうど)であり、女子学習院の教授も務めた伝統和歌派の重鎮の一人でした。この「夏は来ぬ」の頃から、「古今集」以来の正統を継ぐ伝統和歌派は旧派と貶(おとし)められ、いわゆる新派和歌はその伝統を積極的には継承しませんでした。阪正臣のような人がこの世から姿を消してしまう時期に至って「旧派」は衰退し果て、和歌の伝統は事実上断絶したのです。(そう見ると、小琴が阪正臣のもとで習得した教養は実に貴重な伝承であったといえます。すでに埋もれかかっている比田井小琴の事跡もできる限り発掘しておいて、後の世に伝えたいものです。)和歌に清新を取り入れようとして、結果として伝統和歌の急速な衰亡を導いた佐々木信綱ですが、その詩「夏は来ぬ」は、面白いことに、今日の目から見ると実に古典的な意匠で終始しています。新しいものを好み、積極的に新式を推進しようとした人ですが、季節の風情として彼が心に親しいものを集めて歌った時、詩はまさしく伝統的な詩歌の夏の風景を描いたのでした。万葉古今の時代からここまで、日本人の感情はとぎれることなく確かに継承されて来ていたことが分かります。
2 五月の花

アヤメ 堀切菖蒲園

カキツバタ
「夏は来ぬ」は日本の夏の代表的な景物をかなり広く取り上げていますが、ここにない、しかしたいへん重要な花に端午の節句のきまりもの、菖蒲(しょうぶ)・またアヤメがあります。
菖蒲の葉は「水剣」の別名もあるように、切っ先の鋭い刀剣のような形をしているので、悪鬼を斬る魔除けの意味として「蒲剣」といわれます。これを門の上に乗せたり屋根に葺いたりして邪気を払うのが古来の端午の風習でした。今日も行われる菖蒲湯はこれを継承したものです。この菖蒲(しょうぶ)は、やはり菖蒲と書かれるアヤメ(アヤメ科アヤメ)と混同しがちですが、別のサトイモ科の植物です。僻邪に用いられる植物は概してそうですが、菖蒲(しょうぶ)は香りが強いのが特徴です。花はほとんど意識されないくらい地味に根本近くに咲きます。一方アヤメは、「いづれあやめかかきつばた」と美女の風姿に用いられるように、あでやかな美しい花を付けます。あやめ、菖蒲草(あやめぐさ)といった形で万葉時代から歌に詠まれてきた花です。平安時代にはこの植物は水中深く根までを抜き取って贈答品にし、その根の長さを競ったりもしました。また『伊勢物語』や尾形光琳の「燕子花図屏風」で知られるカキツバタもアヤメ科アヤメ属の植物です。紫の花の汁を布に摺り染めにするのに使われたところから、カキツバタという名も「書き付け花」から来たのだという説もあります。花の姿はまさに「いづれあやめかかきつばた」で、アヤメとの区別は容易ではありません。両方をおおまかにアヤメと呼ぶ場面も多かったようです。
今日見られるこの花の仲間にはこのほかにハナショウブなどもあります。花期には幾分かずれがあり、東京葛飾区の堀切菖蒲園では5月14日現在、アヤメとカキツバタは美しく開花していますが、ハナショウブはまだ見頃に至りません。そもそも陰暦五月は現行暦で見れば6月の中旬、端午の五月五日は今年のカレンダーでは6月16日です。本来これからの花なのでしょう。
陰暦五月五日は今年もおそらく梅雨に入っていることでしょう。この類の花は池水によく映え、雨の中に咲くのも似合っています。

ハナショウブ 北山公園(東京都東村山市)


さっきまでここにいて、足下で紙袋に入って遊んでいたみやはどこに行ったのか、探すと、本棚の端の細いカウンターで『日本漢詩選』(北川博邦編 二玄社、平成11年)を開いていました。
花下睡猫 橋本蓉塘(はしもとようとう)
花陰満地午風和
不省三春夢裏過
懶睡応無尸素責
陶鶏瓦犬世間多
花陰[かいん]地に満ちて午風[ごふう]和[わ]し、
省[せい]せず三春[さんしゆん]夢裏[むり]に過ぐるを。
懶睡[らんすい]も応[まさ]に尸素[しそ]の責[せめ]無かるべし、
陶鶏[とうけい]瓦犬[がけん]は世間に多し。
註:三春・・・春季三ヶ月 尸素・・・尸位と素餐。地位にありながら職務を果たさず俸禄だけ受ける者と何もせずに食らう者、すなわち禄盗人と穀潰し。陶鶏瓦犬・・・陶器の鶏と瓦の犬、役に立たないもの。
「花の陰は地に満ちて風も和らぎ、春が夢の間に過ぎてしまったことを振り返りもしない。なまけ眠っているからとて無駄飯食いと責められることもあるまい。役立たずは世間にたくさんいるからな(北川博邦先生訳)」猫が寝ているのはあまりにも当たり前のありふれた景色で、ことさら「懶睡も応に尸素の責無かるべし、陶鶏瓦犬は世間に多し」などと弁護されると、むしろ滑稽な可笑しみが強調されるようです。
春は夢のように過ぎてしまいました。花を惜しむ間もなく忙しい時間に押し寄せられる私たちと同じこの世にいながら、みやはまた初夏には初夏の昼寝をしているわけです。

【文例】(※は本文中に記事あり)
[漢詩]
・※花下睡猫 橋本蓉塘(はしもとようとう)
花陰満地午風和
不省三春夢裏過
懶睡応無尸素責
陶鶏瓦犬世間多
[和歌]
・杜若[かきつばた]衣[きぬ]に摺りつけますらをの
きそひ猟[かり]する月は来にけり
万葉集3921 大伴家持
・※唐衣きつつなれにしつましあれば はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ
『伊勢物語』九段 折句で「かきつばた」
・ ほととぎす鳴くや五月[さつき]のあやめ草
あやめも知らぬ恋もするかな
古今和歌集469 詠み人知らず
・みちのくの安積[あさか]の沼の花かつみ
かつ見る人に恋やわたらむ
古今和歌集677 詠み人知らず
註:花かつみは野花菖蒲(のはなしょうぶ)のこと。
・五月来てながめ増さればあやめぐさ思ひ絶えにしねこそなかるれ
拾遺和歌集1280 女蔵人兵庫
・白玉を包みて遣[や]らば菖蒲草[あやめぐさ]
花橘に合へも貫[ぬ]くがね
万葉集4102 大伴家持 京の家に贈らむ為に真珠を願ふ歌一首
・根を深みまたあらはれぬ菖蒲草[あやめぐさ]
ひとを恋路にえこそ離れね
源順集 あめつちの歌
・雨はるる軒の雫[しづく]に影見えて
菖蒲[あやめ]にすがる夏の夜の月
秋篠月清集 藤原良経
[散文]
・花も糸も紙もすべて、なにもなにも、むらさきなるものはめでたく
こそあれ。むらさきの花の中には、かきつばたぞすこしにくき。
『枕草子』八八段「めでたきもの…」
[訳詩・近現代詩・童謡]
・五月が来た。
樹々が花咲き
青空をわたる
薔薇色の雲。
梢の繁みから
夜鶯[ナハチガル・ナイチンゲール]が歌つてゐる。
柔らかな緑の首蓿[クローバ]の上で
白い仔羊がとびまはつてゐる。
私は歌ふこともとぶこともできない、
病める身を草に横たへ
遠き響きに耳傾けながら
茫然と夢を見てゐる。
ハイネ「序詩」 番匠谷英一訳
・今様うたあぶら絵 高橋由一
心のくまをかきけちて
のぶる絵筆のいのち毛も
あけ紫のいろいろに
染めなすわざこそ楽しけれ
・※夏は来ぬ 佐々木信綱
一 卯の花の匂ふ垣根に
時鳥[ほととぎす]早も来鳴きて
忍音[しのびね]もらす夏は来ぬ
二 さみだれのそそぐ山田に
賤の女[しづのめ]が裳裾[もすそ]ぬらして
玉苗[たまなへ]植うる夏は来ぬ
三 橘[たちばな]の薫[かを]る軒端の
窓近く蛍飛びかひ
おこたり諌[いさ]むる夏は来ぬ
四 楝[あふち]ちる川[かは]べの宿の
門[かど]遠く水鶏[くゐな]声[こゑ]して
夕月[ゆふづき]すずしき夏は来ぬ
五 五月闇[さつきやみ]蛍飛びかひ
水鶏[くゐな]鳴き 卯の花咲きて
早苗[さなへ]植ゑわたす夏は来ぬ
・あの紫は 泉鏡花
あの紫は
お池の杜若[かきつばた]。
一つ橋渡れ。
二つ橋渡れ。
三つ四つ五つ。
杜若[かきつばた]の花も
六つ七つ八つ橋。
あの紫は
お姉ちやんの振袖。
一つ橋渡れ。
二つ橋渡れ。
三つ四つ五つ。
お姉ちやんの年も
六つ七つ八つ橋。
「赤い鳥」大正7年
・初夏 三木露風
藪の筍[たけのこ]、丈のびて
袴の皮が落ちるころ。
李[すもも]の花が白くさき、
柿が青々[あをあを]茂るころ。
柳が塀の外に垂れ、
燕の来るのを待てるころ。
赤鯛、真鯛がよく漁[と]れて
遠[とほ]い町にも売れるころ。
わがふるさとを思ひだす、
白い日かげを見てをれば。
ひい、ふう、みいと、梅の実を、
かぞえて待つたは、何時のこと。
「少年倶楽部」大正10年
・ 夏 佐藤義美
いつ咲いた
雛菊[ひなぎく]
夏がきたの
山、路
青葉[あをば]
遠海[とほうみ]よ
かあさんは
雛菊
すきだった
わたしは
海が
すきだった
「童話」大正14年発表
・酸模[すかんぽ]の咲く頃 北原白秋
土手のすかんぽ、
ジャワ更紗[さらさ]。
昼は蛍が、
ねんねする。
僕ら小学、
尋常科。
今朝も通つて、
またもどる。
すかんぽ、すかんぽ、
川のふち。
夏が来た来た、
ド、レ、ミ、ファ、ソ。
「赤い鳥」大正14年
・おぼえてる 佐藤義美
川[かは]べりの
草道の
草の匂[にほ]ひをおぼえてる
草の上[うへ]まで
水[みづ]がきて
川いつぱいの朝の陽[ひ]も
水[みづ]を離れた
水雉子[みづきじ]が
お空にあがる時の虹
肢[あし]のあいだの
ちいさい虹を
私は今でもおぼえてる
「近代風景」大正15年