

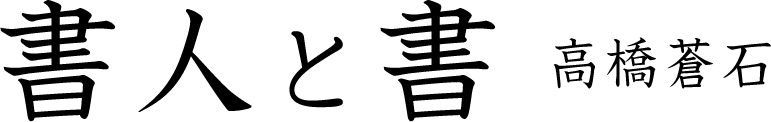
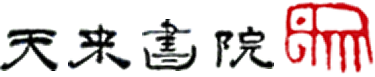

 近藤雪竹2019年9月20日
近藤雪竹2019年9月20日
近藤雪竹 肖像
近藤雪竹(1863~1928)は日下部鳴鶴門の四天王の1人と云われた。他の3人の内、渡邊沙鷗、丹羽海鶴とは同年生まれで、比田井天来(1872~1939)より9歳年長である。
書架に雪竹の作品集が2冊ある。昭和4年に発行になった作品集『雪竹先生遺墨帖』の巻頭に略伝が載っている。抜粋して紹介する。
先生は富壽、字は考卿、雪竹は其の號なり。文久3年6月江戸に生まれる。考は水野藩の士にして、俳諧筆札を善くし、明治維新の後、徒を集めて教授せり。先生の人と為り、恬淡にして和雅、平生放談傲語して自ら推重することを為さず、又名を求め誉を希ひて人に阿諛迎合することを為さず、毅然として自らを守り、座談の間、時に諧謔を弄せらるることありき。幼より学を好み、紀州の藩儒井上韋斎翁に就きて漢籍を学び、日下部鳴鶴の門に遊びて書道を修め、傍ら益を巌谷一六翁に請ふ。上は三代の鐘鼎彝器を始め、下は漢魏六朝より、唐宗明清に至るまで、歷代名家の碑帖、著録等により、一意研精すること四十年、伎倆円熟、学徳兼ね備わる。先生の書に於けるや、各体を善くせざるなきも、就中隷書は最も得意とせらるる所にして、出藍の誉ありき。往年鳴鶴翁は先生の書を評して曰く、余は齢不惑に達して隷書を学びけるが、君は年而立に満たずして既に此の造詣あり、後生真に畏るべしと。一六翁も亦嘗て、先生が楊見山の隷書を臨したるを観て曰く、恰も楊氏の真蹟を観るが如し、前途の進境殆ど測るべからずと。中林梧竹翁も亦、先生の書かれし篆書の大額を観て、称賛措かざりきといふ。若し夫れ先生が書道の為め尽瘁されたる一斑を挙ぐれば、談書会、書道奨励協会、日本書道会、文墨協会、健筆会、法書会、平和博覧会、日本美術協会、日本書道作振会、戊辰書道会等に幹事又は審査委員として関与せざるはなく、入門の士亦三千人の多きに及べり。先生少荘の頃より職を逓信省に奉じ、大正十二年官を退かる。爾来優遊自適、筆硯に親しまれしが、昭和三年十月十四日、渋谷の邸に没す。法名は「大徳院雪窓竹庭居士」といふ。
この作品集は門人他、薫陶を受けた人たち33人が発起人となり、「雪竹先生記念会」から、没後半年で発行された。制作は「晩翠軒」である。発起人には、川谷尚亭、上田桑鳩、辻元史邑、松本芳翠、田中真洲、沖六鵬、半田神来、佐分移山、藤本竹香、益田石華等が名を連ねている。また、雪竹が生前揮毫した、全国にある各種石碑46基の一覧も掲載されている。上に近藤雪竹の肖像写真、左に二点掲載した。右は50代の作。左は還暦前年の歳。力の漲った作品である。

左:龍遊鳳集 右:左思文章金聲玉振 右軍書法鐵畫銀鉤
「現代書の人脈」という欄が、芸術新聞社(雑誌『墨』の出版社)発行の『美術名典』の中にある。現代書というので、明治初年頃からの書道の師弟関係が、家系図のように下へ下へと線で結ばれて伸びている。現在活躍されている作家はゴシック体で、物故作家は明朝体で表示されている。この欄の日下部鳴鶴の時にもふれたが、漢字作家の人脈の中で6割を占めるのが日下部鳴鶴の流れ。鳴鶴門の四天王を含め、十数名がその下に繋がる。その中でこの近藤雪竹と比田井天来(明治5年・1872~昭和14年・1939)の系統が圧倒的に多いのである。雪竹は長く逓信省に奉職していたことは前号に書いたし、門人が3000人もいたことも書いた。現在では考えられないような状況ではないだろうか。雪竹門下では辻元史邑、川谷尚亭、松本芳翠、田中真洲等がいる。中で最大が辻元史邑の系統で、村上三島、広津雲仙、尾崎邑鵬、今井凌雪の各先生が含まれる。現在、読売展(読売新聞社主催)の中でも最大級の派閥を為している。次が川谷尚亭の系統。『書人』誌の源流を遡ると、この流れも大切な部分。手島右卿・高松慕真・南不乗の三兄弟の先生方、山口子羊、炭山南木、金丸梧舟、伊藤東海等がいる。石田栖湖、桑原翠邦先生も、異なった形ではあるが師弟関係と言ってもいいのであろう。松本芳翠の系統には中台青陵、谷村憙齋先生がいる。彼の美術評論家・田宮文平先生は中台青陵先生の御子息である。
雪竹門下の人たちの中で、競書雑誌を発行していた人は何人かいたし、団体を主宰していた人もいた。雪竹はそこで顧問や講習会の講師なども務めていた。川谷尚亭が発行していた『書之研究』という雑誌がある。川谷尚亭(明治19年・1886~昭和8年・1933)に関しては、この「書と書人」の中に登場してもらわなければならない。尚亭は関東大震災後、大正13年に東京から大阪に居を移した。そして早速競書雑誌を発行した。尚亭の主宰する甲子書道会の顧問であった雪竹は、その『書之研究』誌に臨書参考作品を寄せたのであった。左「礼器碑」は厳格な調子、右の「張遷碑」は、古意の中に和らぎがあり、表情豊かな半紙臨書作品となっている。

左:雪竹臨「張遷碑」(『書之研究』より) 右:雪竹臨「礼器碑」(『書之研究』より)